0. はじめに
1. 再分配から承認へ?
2. デッラ・ヴォルペ
3. ルソー
4. アリストテレス
5. トマス・アクィナス
6. メリトクラシーとの関係
7. アクシア問題
8. 分配者問題
9. 分配対象問題
10. 比例性問題
11. 制度の問題
12. アリストテレス派社会民主主義?
1. 再分配から承認へ?
2. デッラ・ヴォルペ
3. ルソー
4. アリストテレス
5. トマス・アクィナス
6. メリトクラシーとの関係
7. アクシア問題
8. 分配者問題
9. 分配対象問題
10. 比例性問題
11. 制度の問題
12. アリストテレス派社会民主主義?
0. はじめに
黒崎勲によれば、「個人の社会的承認を求める権利」は「新しい多様化の理念」とあいまって、能力主義批判と学校選択論とをつないでおり、それは、彼の2冊の著書(『学校選択と学校参加』(1994年)、『現代日本の教育と能力主義』(1995年))を整合的に理解する鍵である、とされているようだ。しかし、多様化はともかく、承認とは教育制度論では耳慣れない言葉である。したがって、せめて多様化と同じ程度には親切な説明の欲しいところだ。たとえば、典拠となっているデッラ・ヴォルペによって承認されるべきとされる「真価(merito)」は、ロールズによって分配の基準としては厳しく退けられた「真価(desert)」とどこがどう違うのか? この問いにたいする応答次第で、承認論は、整合性を確保する鍵であるどころか、それを解体しかねないアキレス腱ともなりかねない。いずれにせよ、少なくともわたしにとっては、能力主義批判と承認論との関係は、多様化論と学校選択論との関係ほどには明晰判明であるとはいいがたい。そこでいろいろ考えてみた。
周知のように、従来アカデミズムの世界で承認論といえば、ヘーゲル研究の一分野を指している。正攻法で攻めるとすれば、最近めざましいヘーゲリアンの文献をある程度フォローすることから手をつけるべきところだろう。が、大変そうなのでやめた。以下では、まず、ナンシー・フレイザーの論考を参照しつつ、ポスト冷戦時代のコンテクストにおける承認論の位置づけを概観し、次いで、デッラ・ヴォルペ→マルクス→ルソー→アリストテレスと遡行して分配の正義について勉強する。また、後半部分では、分配の正義にまつわるさまざまな理論的課題について整理を試みる。
ウィリアム・コノリーが言うように、「アイデンティティとは、社会的に承認されるに至った一連の差異との関係において樹立される」ものである。「アイデンティティが存在するためには差異が必要であり、アイデンティティは自らの確実性を確保するために差異を他者性へと変換する」。したがって、「アイデンティティは、自らが固定しようとする諸々の差異との複雑で政治的な関係において存立している」[Connolly 1991: 64]。 このように承認概念と姉妹関係にあるアイデンティティ・ポリティクスや差異の政治(politics of difference)を提起する議論は、少なくともアングロ・アメリカンの文献においては、従来の解放理論への批判的評価を含んで展開される傾向にある。たとえば、お馴染みのジルー。
アイデンティティ・ポリティクスにまつわる諸問題は,アイデンティティが『階級論理のみには還元されない』ということを認識することに新旧左翼が失敗したということと無縁ではない。…… 1980年代から90年代初頭にかけてのアイデンティティ・ポリティクスは、それが70年代に陥った行き詰まりから何ら回復してはいなかった。[Giroux 1993: 71-72]
こうした状況認識から導かれる抵抗の理論 (批判的教育学)に分配問題への関心が希薄になるのはある意味で当然なのかもしれない。もちろん、完全に無視されているわけではなく、ジルーのめざす民主主義や社会正義といった構想のなかには分配問題もしかるべき位置を占めることになるのであろうが、これまでのところ彼の理論のなかにその明確な姿を見分けることはむずかしい。おそらく、当面の力点がそこにはないからだろう。ところが、黒崎にあっては、承認論は、まずもって、能力主義に代わるべき分配の正義として登場してくる。彼我のコンテクストの違いと言ってしまえばそれまでだが……。
次項でフレイザーの議論を引き合いに出すのは、彼女が「社会的平等と文化的多様性と参加民主主義とを結合することの可能性」[Fraser 1992: 127-128]を明示的に語ろうとしているからにほかならない。
1. 再分配から承認へ?
政治的闘争の目標として、従来の社会経済的平等に代わって、今日、文化的承認がにわかにクローズアップされてきている。だが両者は緊張関係にある。なぜなら、「承認要求は集団的差異化 (group differentiation) を促進する傾向がある」のにたいして、「再分配要求は集団的脱差異化 (group de-differentiation) を促進する傾向にある」 [Fraser 1995: 74] からである (二つの要求の緊張関係は、競争を促進する効果をもつ機会均等要求と、競争と本来的に相いれない能力主義的差別撤廃要求との緊張関係と類推的?)。かくして、「再分配から承認へ?」と題する論考においてフレイザーは次のような問いを立てる。
文化的不正義を矯正することをめざす承認の要求と、経済的不正義を矯正することをめざす再分配の要求との間の関係はどうなっているのか? そして、両方の種類の要求が同時に出されるときに、いかなる種類の相互干渉が起こりうるのか?[ibid.]
もちろん、両者の区分はあくまでも分析的なものである。経済的不正義と文化的不正義とが実際にはお互いに絡み合ったかたちで存在しているということは周知のとおりであり、したがって、「経済的再分配を承認の一表現として取り扱う」アプローチもあれば (たとえばドウォーキン [Dworkin 1978] )、「文化的承認を一種の再分配として取り扱う」アプローチもある (たとえばキムリカ [Kymlicka 1989] )。また、二つの概念の一方が他方に還元されうるのかどうかという問いも問われうる。ホネット [Honneth 1992] によれば、承認は分配を包含しうるという。 (お断り。ドウォーキン、キムリカ、ホネットにかんしてはフレイザー [1995] からの又聞きであり、フォローしていない。)以下に紹介するフレイザーの作業は、こうしたアプローチの手前に位置すべき基礎的な分析ということになる。
まず、「社会経済的な悪分配 (maldistribution) と文化的な誤承認 (misrecognition) の両方を被っている」集合体を「2価的集合体 (bivalent collectivity) 」と呼ぶ [ibid.: 78]。 たとえばジェンダー。ところが、二つの不正義を矯正するための再分配と承認とは反対方向に引き合うから、ここにディレンマが生じる (「再分配-承認のディレンマ」)。なぜなら、「再分配の論理がジェンダーをお役御免にすることであるのにたいして、承認の論理はジェンダー的特種性を価値化 (valorize) することである」 [ibid.: 80] から。
次いで、「肯定 (affirmation) 」と「転換 (transformation) 」という二つの矯正アプローチを導入する。
不正義にたいする肯定的矯正策ということで意味しているのは、さまざまな社会的仕組みの不公平な諸結果を、それらを生成している根本的枠組みを攪乱することなく、矯正することをめざす、ということである。転換的矯正策ということで意味しているのは、不公平な諸結果を、それらを生成する根本的な枠組みのリストラクチュアリングによって、矯正するということである。この対比の核心は、最終状態の結果vsそれらの結果を産出するプロセス、ということろにある。それは、漸進的変化 vs 黙示録的変化ということではない。 [ibid.: 82]
再分配・承認・肯定・転換という4つのアスペクトを組み合わせると4区画のマトリックスを得る [ibid.: 87]。
|
再分配-承認のディレンマを乗り越えるためのシナリオ(上段と下段との組み合わせ)は4通り考えられる。
- unpromising
- the liberal welfare state × deconstruction
- socialism × mainstream multiculturalism
- promising
- the liberal welfare state × mainstream multiculturalism
- socialism × deconstruction
もちろん、実行可能性の問題は決定的に大きい。しかし、要は、基本的な到達目標を明確に定式化することなしには、戦略を練ることも、暫定的な妥協を図ることも不可能である、ということだ。多様性を承認することと、社会経済的平等化とは形式的には矛盾しない。だが、今ここで差異を強調するということが、やがて分配の正義を実現することとつながるのかどうか? また逆に、アファーマティヴ・アクションを人種や性別に左右されない社会という長期的な目標に到達するための過渡期の策として位置づけることは可能だとしても、このような再分配策によって、果たして集団的差異化が流動化するのか? フレイザーが〈リベラルな福祉国家+主流の多文化主義〉の組み合わせを退けるだけでなく、〈多文化主義+社会主義〉や〈福祉国家+脱構築〉という組み合わせを「見込みなし (unpromising) 」とみなしているのはこうした考慮にもとづいている。[ibid.: 88-89]
いずれにしても、モノとモノあるいは人とモノとの関係 (分配問題) と人と人との関係 (承認問題) とを切り離して考えてはならないということ。このことを認めることには何の困難もないが、それを分析的に表現することは容易ではない(一方を括弧に入れておいて、片方だけを論じるのは誰にでもある程度はできる)。アイリス・ヤング批判の含みをもつのこのフレイザー論文は、両者の一連の論戦の一環をなすものであるが、この興味深いやり取りの検討については別項に譲るとして、ここでは貴重なアイテムとしてひとまずフレイザーのマトリックスを道具箱にしまっておくことにしよう。
2. デッラ・ヴォルペ
デッラ・ヴォルペ『ルソーとマルクス』 [RM] の中心的主張は「序論」において端的に次のように述べられている。
(平等主義的) 自由にかんするルソーのメッセージの豊かな内容は、人の《真価[merito]》の普遍的 (民主主義的) 要求、すなわち、それぞれ独特の真価と必要をもった各々の人間個体すべてを (社会的に) 承認 [riconosciment] するという要求のなかに見いだされるべきだろう。そうすることによって、共産主義社会における労働生産物の (相異なる) 各個人への比例的 [proporzional] 配分は……まさしく人の真価というルソー的要求の歴史的完成を表現することになる。[RM: 17(原書のページ)/21-22(訳書のページ)]
何と何が比例関係にあるのか? 社会的不平等と自然的不平等である。これはルソー『人間不平等起源論』 [DI] の結論部分に依拠している。
ただ実定法のみによってオーソライズされている人為的不平等 [inegalite morale] は、それが自然的不平等 [inegalite Physique] と同じ比率で釣り合っていないときにはいつでも自然法に反しているということになる。この区別は、政治的社会に生きる [police] すべての人民のあいだに君臨しているような種類の不平等について、この点でどう考えるべきかを十分に決定するものである。[DI: 193-194]
デッラ・ヴォルペは、ルソーのこの平等主義を、「反水平化的平等主義」 [RM: 79/104]とか、「諸人格を調停する平等主義」 [RM: 84/111]と呼ぶ。
「真価」 とは何か? 人々がもつ 「諸々の力や才能等々」 [RM: 41/54] のことであり、ルソーのいう 「自然的不平等」 とは、要するに 「諸々の力や真価の自然的不平等、すなわち人間のパーソナルな差異」 [RM: 82/108]のことである、とされる。
「真価」 はいかにして尺度されるのか? デッラ・ヴォルペは、「労働を無差別にすべての個々人の属性であり、各人が自分のパーソナルな能力や真価を実現するための、要するに人格となり、自らを自由にするための手段的な徳であるとみなす」 ことにより、「真価-労働」 という 「価値論的2項式」 をもちだす [RM: 88/117]。そうして、ルソーの結論を次のようにまとめている。
各々の市民のすべての社会的地位(=人々の間にある不平等 inegalite parmi des hommes) は、その市民が自分の諸々のパーソナルな真価とパーソナルな諸条件 (=人々のもつ不平等 inegalite des hommes) に比例して社会におこなったサービスにもとづいて調整されるべきだ。[RM: 82/108]
念のため、ルソーの原文をみてみる (『不平等論』 の最後の注) 。
国家のすべての成員は、自分の諸々の才能と力に比例してサービスしなければならないのだから、これを市民の側からみれば、彼らは自分のサービスに比例して区別され処遇されてしかるべきである。…… 市民たちの地位 [les rangs] は、彼らの個人的な真価にもとづいて規整されるべきではない。もしそうすれば、為政者に法律をほとんど恣意的に適用する手段を与えてしまうだろう。そうではなく、市民たちの地位は、彼らが国家にたいしておこなう現実のサービス、より正確な評価を受けられる現実のサービスにもとづいて規整されるべきである。[DI: 222-223]
引用の第二文は、「人々の人格について判断することを為政者に禁じる」 [ibid.] ということの帰結である。したがって、比例関係の情報的基礎としては 「現実のサービス」 が採用されることになる。デッラ・ヴォルペの 「真価-労働」 という 「価値論的2項式」 は、このことの別の表現とみなされうる。デッラ・ヴォルペの読み方は要するにこういうことである。
社会的不平等は (真価の) 自然的不平等に比例すべきである。
社会的貢献度は真価に比例する。
ゆえに、社会的不平等は社会的貢献度に比例すべきである。
社会的貢献度は真価に比例する。
ゆえに、社会的不平等は社会的貢献度に比例すべきである。
ところで、ルチオ・コレッティは、デッラ・ヴォルペの先に紹介したようなルソー解釈に賛意を表しつつも、ルソーとマルクスとの 「相同性」 の主張にたいしてはこれを厳しく批判している。
ルソーが個人の 『真価』 の社会的承認の必要性をめざしているのにたいして、マルクスは逆に、個人の 『必要』 の社会的承認に訴えている。二人とも、個人と個人の間に存在する 『差異』 の承認にもとづく平等を切望している。しかし、その点において一致しているとしても、次のような相違点をめぐって論争がある。すなわち、ルソーは、社会が多様な 『真価』 を承認することができ、結果的に、諸個人が提供する 『サービス』 に応じて、つまり彼らの多様な能力と生産高に応じて社会的『地位』を分節化することができるように、個人的差異を考慮に入れることが必要だと判断している。それにたいして、マルクスは、まさしく、もっとも資質に恵まれない人々の『必要』に向き合うため、そして、いかなるヒエラルキーの発生をも妨げるために、社会が将来において、個人と個人の差異を考慮に入れることができるようになるだろう、と予言する。[Colletti: 261]
そうして 『ドイツ・イデオロギー』 から次の部分を引用する (コレッティはマルクスによるものとしているが、実はモーゼス・ヘスが執筆したと言われている)。
共産主義があらゆる反動的社会主義と区別されるもっとも本質的な原理の一つはどこにあるかといえば、それは人間の自然〔ほんせい〕のうえに基礎づけられた次のような経験的見解である。すなわち、頭および一般に知的能力の差異は、胃および肉体的諸要求 [Bedurfnisse] の差異をなんら条件づけるものではないということ、したがって、われわれの現存の諸関係が基礎になっているまちがった原則 『各人にはその能力に応じて』 という原則は、これが狭い意味での享受に関係しているかぎり、『各人には必要 [Bedurfnis] に応じて』 という原則に変更されなければならないということ、言い換えれば、活動における、労働における相違は、いかなる不平等の根拠にもならず、所有と享受のいかなる特権の根拠にもならないということである。」『マルエン全集』3巻: 586-587]
コレッティの批判の当否はともかく、そのような読み方がありうるということはうなずけることだし、実際、1960年代末の 「暑い秋」 において、労働運動や学生運動の路線はデッラ・ヴォルペの主張に鋭く対立することになったという [アルカーロ: 661]。
たしかに、「《各人からはその能力に応じて》というマルクスの定式のなかへの、各人の諸々の真価や才能や能力の社会的承認というルソーの規準の凱旋」 [RM: 106/142] とデッラ・ヴォルペが書くとき、そこには《各人へは必要に応じて》の部分が脱落している。もちろん、「個人そのものの社会的承認」 [RM: 41/55] の 「個人そのもの」 のなかに 「必要」 を含める解釈も可能ではあろうが、デッラ・ヴォルペ本人が明示的に述べていない以上どうしようもない。思うに、決定的であったのは、「真価-労働」 というあの「価値論的2項式」 の導入であろう。 ところが、この2項式は、彼がマルクスに忠実であることの証左でもある。してみれば、マルクスのあの定式がマルクス的でなかったということか?
ところで、後藤道夫によれば、「社会の成員の全員が能力に応じて働き、労働に応じて受けとるという共産主義社会の第一段階の想定は、むしろメリトクラシーそのもの」 とみなされうるものだし、また、第二段階における 「メリトクラシーを私的所有の廃絶によって実現するという志向と、才能の差にかかわりなく平等な処遇を実現するという志向との媒介は、マルクスにあっては、生産力のきわめて高度な発展という点に求められているのであり」、そこで想定されているイメージは 「メリトクラシーは人為的に 『廃棄』 されるのではなく、生産力の発展とともに 『死滅』 する」というものに近い [後藤: 540, 542]。 したがって、今日の社会と自然の現状に鑑みるとき、ルソーではなくマルクスを選べばそれで済むというほど問題は単純ではない。
当然のことながら、未来史的な条件を捨象して、すなわち資源の稀少性という条件下において、マルクスの定式を文字通りに実行しようとするときには困難が生じる。たとえば、ある資格を要する職にたいして、有資格志願者が殺到したとき、何を基準に採否を決定するのか? 求人側のニーズか、それとも求職側のニーズか? 求職側からみれば、前者は 「能力に応じた」 採用ということになり、後者は 「必要に応じた」 採用ということになる。マルクスの定式に潜むこうした難点を指摘したうえで、マイケル・ウォルツァーは、「社会的に承認されたニーズ socially recognized needs」 という観念を導入し、先の定式を次のように修正する。「各人からは彼の能力 (または彼の資源) に応じて、各人へは彼の社会的に承認されたニーズに応じて」 [Walzer: 91]。つまり、「コミュニティが、必要とされるなんらかの財を供給することをいったん引き受けたならば、そのコミュニティは、それを必要としているすべてのメンバーにたいして、彼らの必要に比例してその財を供給しなければならない」 [ibid.: 75]。 ただし、そうしたニーズは、「歴史的な・一定の形態」 [ibid.: 65] をまとっている。言い換えれば、「いかなるニーズが承認されるべきなのかということについてのア・プリオリな規定は存在しないし、適切な供給レベルを確定するア・プリオリな方途も存在しない」 [ibid.: 75]。 この意味において、「ニーズはとらえどころのないものであり」 [ibid.: 66]、 「コミュナルな施策の形態は、これまでも変化してきたし、これからも変化しつづけるであろう」 が、他方で、この変化は 「自動的」 には生じない [ibid.: 91]。 こうした変化は 「つねに政治的な議論と組織化と闘争の問題である」 [ibid.]。 このように構想される「社会的に承認された必要」が、もはや、「真価」 (=自然的!) の要素とみなされうる (?) 「必要」 とは似て非なるものであるということは言うまでもない。
3. ルソー
ここからはデッラ・ヴォルペからいったん離れて、しばらくのあいだルソーの議論に即して話を進める。
ルソーは、『コルシカ憲法草案』 [CC] のなかでも、「各人は、ただ国家にたいするそのサービスに比例してのみ、共同財産にたいするその持ち分を受けとる」 [CC: 931] と繰り返している。この提案は、「《各人にはその労働に応じて》という社会主義の格律を思い起こさせる」 [Delaporte: 291] 響きをもっており、後藤によれば、後者は 「メリトクラシーそのもの」 である。ルソーはメリトクラートなのか?
ところが、彼は 『不平等起源論』 執筆の前年に次のようにも書いている。
本来、徳にもとづくべき名誉を、ひとたび才能が侵すと、だれしもが人に気に入られる人間になりたがり、徳の高い人間になろうとしなくなる。そこからなおまた、本人の力ではなんともならない諸々の特質のみが人々のなかで報いられるというもうひとつ別の筋の通らぬことが生じる。というのも、才能は生まれながらのものであって、徳のみがわれわれの意志に属すものだからである。[PN: 966]
つまり、「ルソーは、人間の連帯を打ち砕く才能の差異のなかに、人類が被るあらゆる不正義の原因を見る」 [Galliani: 297-298] のである。ここから、ルソーにとって、才能の自然的差異は 「不平等の恣意的な言い訳」 にすぎず、したがって、ルソーにとって「メリトクラティックな社会は解決ではなく問題であり、治療ではなく病気である」 [Hulliung: 134] という解釈も成り立つ。わたしもこの解釈をとる。この場合のキーワードは 「徳」 である。
その自然からすれば弱く、その意志によって強い存在だけに徳は帰属する。正義の人の真価 [merite] が存するのはまさしくそこにおいてである。[EE: 817]
ルソーが、《真価》に応じた公共財 (官職や名誉を含む) の分配を支持するのは、《真価》と《徳》との間にこのような関係を立てているからにほかならない。また、「国家にたいするサービス」 は 「市民の義務」 であり、その遂行はこの意味での《真価》の発揮として有徳な行為と位置づけられる。すなわち,報いられるべきはこの有徳な行為である。ただし、報いられるべき諸個人の行為は、有徳という性質において等しいのであって、その程度は自然的資質の差異に応じて異なる。しかしながら、いかに自然的資質に恵まれた者の行為でも、そこに有徳な意志がなければ、報いられるに値しない。わたしとしては、『社会契約論』 [CS] の以下の記述はそのように読まれなければならない、と考える。
社会契約の性質からして、主権のすべての行為、すなわち一般意志のすべての真正の行為は、全市民に等しく義務を課し、彼らを等しく処遇する。[CS: 374]
なお、ルソーによれば、《徳》に報いるに 「金銭的報酬」 はふさわしくない。彼は、「身につける印によって真価と徳を際立たせる」 という 「真価の貴族制 l'aristocratie du merite」 [Hulliung: 294] とでも呼ぶべきものを提案している [GP: 1007]。
もっと経済的なことがらに話題を移そう。ルソーは、平等を 「権力と富が絶対的に同一であるという意味に解してはならない」 [CS: 391] と明言し、社会的無秩序にいたらない範囲において ─ 「すべての人々が何ほどかのものを持ち、しかもだれもが持ちすぎてはいない」 [CS: 367] ─ 富の不平等を認める。富の平等を認めないのは、そのようなことは「物事の自然のなかに存在しない」 からであり、極端な不平等を認めないのは、それが「市民的徳 ─ 一般意志の形成と実施に協力しようという気にさせる態度 ─ を破壊する」 [Trachtenberg: 167] からである。この場合のキーワードが 「比例」 である。『不平等起源論』 では、この 「比例」 は 「市民の地位」 分配に関連して用いられていたが、『政治経済論』 [EP] においては、税制にかんして 「比例」 の語が駆使されている。その論述は、「比例」 という語に託してルソーが描いている正義の内容を解き明かそうとするにさいして、重要な示唆を与えてくれる。
「祖国は自由なくして、自由は徳なくして、徳は市民なくしては存立することができない」 [EP: 259] との考えに立脚し、「市民たちが祖国のなかで享受する諸々の利益によって、彼らが自国を愛するようにせよ」 [EP: 258] と呼びかけるルソーは、「ゆえに」 とつづけて、「政府のもっとも重要な仕事の一つは、財産の極端な不平等を防ぐことにある」 [EP: 258] と明言する。そして、その防止の方途の一つとして、独自の税制構想を展開する。
ルソーは言う。
頭割りの課税が諸個人の資力に正確に比例しているならば……それはもっとも公正なものであり、したがって自由な人間にもっとも適したものである。この比例関係は最初のうちはひじょうに容易に守られるようにみえる。なぜなら、その目安は各人が世の中で占める身分にかかわっており、つねに公的なものだからである。[EP: 270-271]
そこには考慮されるべき三つの要素がある。
第一に、すべての事情が等しければ、他人の10倍の財産をもつ人は10倍多く支払うべきだという量的な関係を考慮しなければならない。第二に、用途の関係、すなわち必要なものと余分なものとの区別を考慮すべきである。たんなる必要物しかもっていない人は、なにも支払うには及ばない。余分なものをもつ人にたいする課税は、必要とあらば、彼の必要分を越えるすべてのものにまで達することができる。…… 第三の関係は、各人が社会的結合から引き出す効用の関係であって、それはまったく考慮されていないが、つねにまっさきに考慮されなければならないものである。……社会のあらゆる利益は有力者と金持ちのためのものではないだろうか。あらゆる有利な職務は彼らだけによって占められていないだろうか。あらゆる恩恵や義務の免除は彼らのために取っておかれてはいないだろうか。公共の権威はすべて彼らに有利ではないだろうか。[EP: 271]
このうち、第一の要素のみが、通常の意味における比例関係を構成している。それにたいして、第二の要素についての考慮は基礎控除をおこなうべしという提案を導く。こうすることによって「すべての人々が何ほどかのものをもち、しかも誰も持ちすぎてはいない」というあるべき社会状態の実現が図られる。これは、単純な比例関係にたいする修正となる。さらに、第三の要素についての考慮は、すべての市民に等しい義務を課し等しい権利を与えるという社会契約の基本的発想へとつながる。国家へのサービスに応じて個人を処遇するというのはその一つの制度的表現とみなされうる。
かくして、ルソーは次のように結論する。
これらすべてのことを注意深く結びつければ、租税を公正で真に比例的な仕方で割り当てるには、課税はたんに納税者の財産に比例しておこなわれるべきではなく、それに加えて、彼らの条件の差異と彼らの財産のうちの余剰分との複比例でおこなわれなければならないということがわかるだろう。[EP: 273]
こうした構想を 「比例関係」 と呼べるかどうかはさておき、ルソーのいう 「公正」 な比例関係が 「複合的」 なものであるということは確認することができる。そして、そこにはたしかに 「必要」 への配慮を読みとることができる。だが、それでもなお、分担の場面におけるこの配慮を、分配の場面における 「必要に応じて各人へ」 と類推解釈するのはやりすぎだ。最低生活水準を平等に保証したうえで、あとは労働に応じて、ということになると考えるほうが妥当だろう。したがって、ルソーの平等論を、共産主義段階の第二段階と結びつけるデッラ・ヴォルペの読み方には無理がある。かといって、ルソーの構想を共産主義の第一段階 (社会主義) ─「メリトクラシーそのもの」─ に比するのも適切ではなかろう。いささか逆説的だが、彼は私的所有を認めたがために、そこから発生する社会的不平等を是正せざるをえず、結果的に 「必要」 を考慮に入れる次第となっている。
以上、ルソーのテクストから浮かび上がってくる彼の正義コンセプションと、デッラ・ヴォルペの描くそれとの相違点に着目して論を進めてきた。しかしながら、両者は (そしておそらくはマルクスをこれに加えてかまわないだろう) 交換の正義ではなく分配の正義を社会秩序の構成原理に据えるという観点を共有している。この観点は、英語版 『ルソー著作集』 の編者が注記しているように、「分配の正義」 と 「交換的正義」 もしくは 「是正的正義」 との 「古典的区別をキッパリと批判しつつ,真価にたいする報償は『正義によって受けてしかるべきものではなく、恩寵により与えられるものである』 (『リヴァイアサン』15章) と述べる」 ホッブズの観点、すなわち 「政治的生活において唯一レレヴァントな基準は、法律の諸主体のすべてを、その個人的な値打ち (personal worth) の如何にかかわらず等しく取り扱う是正的正義である」 とする近代的観点に対立するものであり、「徳という古典的観念が依然としてしかるべき位置を占めることができるように、近代的諸原理を用いようと試み」 るものである [Masters and Kelly: 188]。
この古典的観念の近代的再生を可能にしているものは何か? わたしが思うに、それは、〈真価〉-〈労働〉-〈徳〉のトリアーデである。このうち近代に特有なものは言うまでもなく〈労働〉であり、これを介在させたのは、デッラ・ヴォルペの言葉を借りれば、「価値論的 (assiologico) 」 な判断であった。ところが、こうすることによって、分配の正義には、なにかしらメリトクラティックな臭いがつきまとうことになったように思われる。もともとの古典的観念はいったいどのようなものであったのか? 別の価値論的判断をもってきて、そのオルタナティヴな再生を考えることはできないものだろうか?
4. アリストテレス
デッラ・ヴォルペ、マルクス、ルソーの所論の典拠として位置づけられるアリストテレスの正義論を、有江大介『労働と正義 ─ その経済学史的検討』 (1990) に依りつつ読んでみる(便宜のためアリストテレスの用語法については有江にしたがう)。
アリストテレスが『ニコマコス倫理学』 [NE] のなかで、分配的正義、是正的正義、応報的正義を区別したことはよく知られている。これら三種の正義の関係を見定めることを第一の課題とする。
まず 「分配的正義」 について。あるもの(共有財)が二人に分配される場合、「その事物における」 価値による比例と 「その人々にとっての」 価値にもとづく比例とが等しくなるように分配されなければならない [NE: 1131b4-5]。今、当事者a、bの価値をA、B、それぞれが受け取るものの価値の大きさをC、Dとすると、
A:B=C:D (1)
A:C=B:D (2)
A:B=A+C:B+D (3)
A:C=B:D (2)
A:B=A+C:B+D (3)
(3) の比例式をアリストテレスは 「幾何学的比例」 と呼んでいる。ポイントは、「ポリス共同体の成員には価値的な差異」 があり、「分配的正義の対象となる種類の財については……“物と物との関係”によってではなく“人と人との関係”の文脈で事前的に分配比率が決定される」 [有江: 25-26] というところにある。
次に 「是正的正義」 について。私人間の取引にかかわる正義であり、相互取引における不正な利得と損失の是正をその内容とする。これをアリストテレスは 「算術的比例」 (等差中項または平均) として説明する。
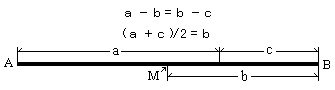
つまり、「是正的正義」 が扱うのはモノとモノとの関係であり、そこでは 「当事者の実質的な価値序列ではなく、単に形式的な公正さ、量的な等価性が問題とされるという点に、共有物分配の場面で人々の価値序列こそが問題となる『分配的正義』との質的な違いを見るべきである」 [有江: 27]。
三番目、「応報的正義」 について。これは、有江によれば、「“人と人との関係" と “ものとものとの関係" の総合」 [有江: 27] である。すなわち、正義の意味合いとして当事者の価値性が重んじられという点では 「分配的正義」 の側面をもっているが、他方、正義の場面として想定されているのは私的取引関係であり 「是正的正義」 の領分と重なる。また、ここでの取引は異種のモノの相互取引である。以上を表にして示すと次のようになる [有江: 28]。
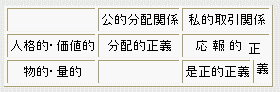
したがって、「『応報的正義』 は、『分配的正義』 の人格価値性すなわち 『幾何学的比例』 の側面と、『是正的正義』 の量的形式性すなわち 『算術的比例』 の側面の双方を併せもつと言えよう」 [有江: 29]。
交換比率はいつ決定されるのか? 交換以前においてである。「比例関係が結ばれるのは、双方が交換を行なった後ではなく、双方がまだ自分のものを持っているときでなければならない」 (1133b1-2)。
等価交換なのか? 等価交換である。このことをアリストテレスは 「対角線の組合せ」 という独特の説明法で論じている。「比例にかなった報償は対角線の組合せによってなされる」 (1133a5-6)。
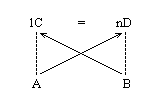
Aを大工の価値、Bを靴工の価値、Cを家1単位の価値、Dを靴1単位の価値、nを靴の数とすると、1C=nD となっており、ここから
A:B=C:D
A:C=B:D
A:C=B:D
が導かれる。このとき、幾何学的比例が成立している〈人格的な価値序列(B=A/n)に応じて、1単位の異なる所産がある(D=C/n)〉と同時に、等価交換が成立している〈C=nD〉。
このような 「応報的正義」 の内容と構造を有江は次のようにまとめる。
二人の異なった人々の異なった所産の交換において
i) 人と人との関係では彼らの人格的価値=貢献度=技能に対応した『幾何学的比例』が存在し、
ii) 彼らの所産であるものとものとの交換関係では 「算術的比例」 による量的平均たる等価交換が行なわれ、
iii) 交換の結果、それぞれの価値に対応した報償=応報がなされた。
ということになろう。/要約すれば、等価交換を媒介に 「応報」 が行なわれるのが 「応報的正義」 ということになる。そこで 「幾何学的比例」 が維持されることによってポリス共同体を維持するという目的がかなうことになる。 [有江: 31]
i) 人と人との関係では彼らの人格的価値=貢献度=技能に対応した『幾何学的比例』が存在し、
ii) 彼らの所産であるものとものとの交換関係では 「算術的比例」 による量的平均たる等価交換が行なわれ、
iii) 交換の結果、それぞれの価値に対応した報償=応報がなされた。
ということになろう。/要約すれば、等価交換を媒介に 「応報」 が行なわれるのが 「応報的正義」 ということになる。そこで 「幾何学的比例」 が維持されることによってポリス共同体を維持するという目的がかなうことになる。 [有江: 31]
注意を要するのは、「応報的正義」 において、「交換取引に供せられる財貨と対応するのは、その財貨の生産者の労働や技能というよりそれらを含めた人格的な価値である」 [有江: 39]。 言い換えれば、
「対角線の組合せ」 という言葉が象徴するように、ある価値を持った生産者Aとその所産とが直接に結びつけられているのではなく、生産者と交換の相手方の所産Dとが結びつけられているのである。このことは、アリストテレスが生産者Aと所産B(ママ)の価値とを労働投入とそれによる価値というように垂直的に理解していたとは、必ずしも言えないことを示している。むしろ、…… アリストテレスの場合、労働を考えられるにしても近代的な意味での生産のためのコストと見ているのではなく、ポリスを構成する個々人の人格的評価である点に注意すべきだと思う。 [有江: 52-52]
アリストテレスでは、靴職人と大工の例に見る生産者とその所産との関連においては、一見するとそれぞれの生産労働がその所産の値打ちを規定しているようでいて、実はそうではなく 「幾何学的比例」 を構成する当事者の価値は第一義的には共同体への貢献度などの人格的評価なのである。この事例では技能や貢献度の差として人格的価値を広くとらえることも可能だが、生産労働が直接所産に対応しているわけではない点に留意すべきと思う。奴隷社会の人間であるアリストテレスが本来、生産やものの制作活動をポリス共同体における社会生活から排除していたということを想起されたい。ただ、質的な種差のある人格的関係のほうが、通約後の 「算術的比例」 たる等価交換の物的関係より本質的であるのは言うまでもない。財貨の交換比率が問題になるとき、事前にそれを決めるべき生産者=制作者の種差が問題にされるのだが、アリストテレスの場合、それが労働投入の差にのみ一意的に還元されるのだとはどこでも言っていない。近代以降の解釈者がそのように読むのである。 [有江: 42]
アリストテレスでは、靴職人と大工の例に見る生産者とその所産との関連においては、一見するとそれぞれの生産労働がその所産の値打ちを規定しているようでいて、実はそうではなく 「幾何学的比例」 を構成する当事者の価値は第一義的には共同体への貢献度などの人格的評価なのである。この事例では技能や貢献度の差として人格的価値を広くとらえることも可能だが、生産労働が直接所産に対応しているわけではない点に留意すべきと思う。奴隷社会の人間であるアリストテレスが本来、生産やものの制作活動をポリス共同体における社会生活から排除していたということを想起されたい。ただ、質的な種差のある人格的関係のほうが、通約後の 「算術的比例」 たる等価交換の物的関係より本質的であるのは言うまでもない。財貨の交換比率が問題になるとき、事前にそれを決めるべき生産者=制作者の種差が問題にされるのだが、アリストテレスの場合、それが労働投入の差にのみ一意的に還元されるのだとはどこでも言っていない。近代以降の解釈者がそのように読むのである。 [有江: 42]
有江がここで 「近代以降の解釈者」 として論及するのはマルクスである。
家がベッドにたいしてある同等なものを表わしているのは、この両方のもの、ベッドと家とのうちにある現実に同等なものを家が表している限りでのことである。そしてこの同等なものは ─ 人間労働である。[Marx, 1975, 74/81]
『資本論』 のこの箇所にかんする有江の評釈。
この特色の第一は、財貨の貨幣による統一的評価の前提に「共通の実体」たる本質としての 「人間労働一般」 が位置づいている点である。確かに、本質を人間に直接係わる準位で規定するところはアリストテレスと共通ではある。しかし、第二に、種差のないいわば質量 (Materia) にあたる労働一般を本質に位置づける点は、アリストテレスの対極にあると言える。[有江: 42]
このことを踏まえて、『ゴータ綱領批判』 のあの箇所を読んでみると、共産主義の 「第一段階」 についてみれば、
両者における人格的価値の内容の違いを度外視すれば、形式的構造としてはこれはアリストテレスの 「応報的正義」 そのものであると考えてよい。マルクスは、ここに残存する、貢献度の差異に応じた分配という理念に異議を唱えるのである。[有江:45]
共産主義の「より高い段階」について。
「第一段階」 との比較で言えば、この段階では等労働量交換はない。すなわち 「算術的比例」 の成立する場面が存在しないのであって、あるのは 「幾何学的比例」 だけである。ただし、この場合は貢献度の尺度が労働ではなく、 「必要」 ないし 「欲求」 ということになる。つまり、各人のさまざまに異なった必要、欲求、需要に応じた分配が、貨幣や交換取引による結び付きのないところで社会の名において行なわれる。これが “真の平等" である。明らかに,アリストテレスの 「分配的正義」 に相似的であるといってよい。[有江:46]
したがって、コルネリュウス・カストリアディスが言うように、マルクスは 「アリストテレスが 『ニコマコス倫理学』 で描いた地平線で、これが措定した範疇によって」 論じており、「本質的な点としては、その答えは第五巻のいくつかの文章の敷衍でしかない」 [Castoriadis: (訳)342] といってもよかろう。
先にどこかで、共産主義イメージに関連して、必要に応じた無制約の消費を支える生産力の無限の発達が想定されているということに触れたが、ここでもう一つ、「労働することが社会の構成員の分配のための一元的な資格要件になっている」 [有江: 48] ということに注目しておきたい。こうした労働にたいする思い入れは、「マルクスにおける労働に対する倫理的・哲学的な意味付与の強さを表していると思われる」 [有江: 46]。
5. トマス・アクィナス
有江によれば、「“労働⇔正義⇔値打ち”」 というトリアーデを編み出した、すなわちある行為を正義とする力を労働に付与したのはトマスであり、その意味でマルクスは 「最後のスコラ学者」 [有江: 97] であるという。あるいはトマスを最初のモダニストと呼ぶことができるかもしれない。ここでも、トマスの 『倫理学註解』 [Com.] と 『神学大全』 [S.T.] とを読み解く有江に依拠する。
アリストテレスの正義論を注解するという形で展開されるトマスの正義論は、前者における三種の正義のうち、「応報的正義」 を採用していない。また、「是正的正義」 は概念的に拡張され 「交換的正義」 として語られ、これに圧倒的なウエイトがかけられることになる。
アリストテレスの 「分配的正義」 および 「幾何学的比例」 への注解。
したがって、たとえばAを1つの項として2ポンド、同様にBが1ポンドとしよう。そこでCを一人の人間たとえば2日働いたソクラテス、Dを1日働いたプラトンとすれば、双方における2重に比例関係によって、A:B=C:Dとなり、入れ換えればA:C=B:Dとなる。……こうして、……次のことが正しく言える。A:C=B:D、すなわち〈2ポンド〉:〈2日労働した男〉:〈1ポンド〉:〈1日労働した男〉 [Com., V-V, c.941]
これは、「たしかに比例式としてはアリストテレスの 『幾何学的比例』 そのものではある。しかし、ものとものとの比例を基礎づける人と人との関係における比例が、アリストテレスの場合のような共同体における人格的価値序列としてではなく、ものを作るのに費やした労働の大きさの違いとして端的に示されている点が違いとして挙げられる。つまり、生産物の交換ではなく分配をめぐる議論に際して早くもこうした例を示すことは、ある財貨の評価とそれを作るのに要した労働ないし費用とを関連づけるという発想を、トマスがある程度強く持っていたことを意味して」 [有江: 72-73] いる。
トマスが、アリストテレスの 「是正的正義」 という用語ではなく、「交換的正義」 という用語を採用しているのには、トマスが使用したラテン語テクストにおける翻訳の問題がからんでいたようだが [有江: 100-101]、ここで重要なことは、「交換的正義」 の適用範囲の拡張と、「応報的正義」 の不採用とが密接に結びついていたということである。端的にいえば、トマスにとって 「応報」 とは 「交換的正義」 である。
応報が分配の正義の中に占める位置はない。分配的正義では均等性は、〔交換的正義のように〕物が物に対して、あるいは対抗行為が能動行為に対して持つ比例〔proportion/proportio〕に即して捉えられるのではなく( 『応報』 が語られるのはこのとき)、……諸々の物が諸々の人格に対して持つ比例性〔proportionalitas〕に即して捉えられるからである。[S.T., II-II, 61, 4, Resp.]
もし、共同体に貢献した人間に対してその貢献への報酬が与えられるとしたら、それは分配的正義ではなく交換的正義の行為である。なぜなら、分配的正義が問題とするのは、費やしたものと受け取るものとの間の均等性ではなく、ある人間と他のある人間とが、それぞれの人格的評価に応じて受け取る物の間の均等性だからである。[ibid., 61, 4, ad 2]
もし、共同体に貢献した人間に対してその貢献への報酬が与えられるとしたら、それは分配的正義ではなく交換的正義の行為である。なぜなら、分配的正義が問題とするのは、費やしたものと受け取るものとの間の均等性ではなく、ある人間と他のある人間とが、それぞれの人格的評価に応じて受け取る物の間の均等性だからである。[ibid., 61, 4, ad 2]
アリストテレスとの相違は明白である。トマスは、「 『応報』 の根拠を、予め在る人格的序列にではなく 『仕事』、すなわち諸物に直接関係する行為に見ている」 [有江: 75]。 すなわち、
実際には量的等価を越える 「応報」 の要素を含むこの場合に対しては、財貨の供給者の人格的価値序列への配慮はそれ自体としては取り上げず、人格に関連してはいるが相対的に区別された 「仕事」 の評価が、取引における形式的な公正さである量的な均等を実現するための根拠の位置に置かれている。トマスにとって重要なのは行為に即した交換の等価性なのである。 [有江: 78]
アリストテレスにあっては 「分配的正義」 の領域にあった共同体と個人との関係をも 「交換的正義」 に含ませてしまうということは、「結果として経済行為はすべて原理的には 『交換的正義』 の問題であると言うことに等しい」 [有江: 82]。 この 「分配的正義の後退と交換的正義の自立化」 [有江: 95] とも呼ぶべき転換に含意されるトマスの新知見を、有江の評言から抜き出し、〈労働神話の生成〉 (「労働神話」という語は江原由美子 [1990] から借りた。有江の用語では 「アルバイト・コンプレックス」 である) と〈抽象的個人の生成〉という二つのタイトルのもとにまとめてみよう。
〈労働神話の生成〉
「交換的正義」 の均等性すなわち等価が主要にはまず労働と費用に還元された上でその量によって決められることから帰結する、当事者の人格自体の評価よりも彼らの行為の過程、働きの過程の評価が重視される……。つまり、アリストテレスの人格的価値序列に即した 「応報」 とは異なった、行為の過程(労働と費用)の評価に対応した 「応報」 こそ、トマスにおける交換取引における正義の内容である。[有江: 82-83]
……労働なり費用なりの支出には対応給付があるべきだ、という規範的な考え方……。簡単に言えば、労働には報酬が自明のように認められている,ということ…… [有江:91]
労働[labor] は 苦痛であるということ……。…… 労働は労苦であるが故に代償を得ることができる……。……労働自体がある行為を正義とする力を持っている…… [有江:92]
労働とその報酬との関係をものとものとの交換関係と同一視している……。ものとものとの関係の正義は等価交換であったから、労働とその報酬との関係でも等価交換が求められる。つまり、労苦としての労働という犠牲に対応した報酬が 「交換的正義」 の原理に則って考えられる。これは社会関係を考える上で、一つの理論的飛躍である。つまり、異なった労働による異なった財貨同士の交換取引において、ものとものとの関係と、人と人との関係が「交換的正義」という一つの原理によって関係づけられるからである。アリストテレスでは人格的序列に即した「分配的正義」と、形式的・量的均等による「是正的正義」の両面を持った「応報的正義」によって説明されていたところを、量的均等の「交換的正義」のみによって説明する……。いわば、社会の経済的諸関係を「交換的正義」という物象的な関係のみによって説明する……。 [有江:92]
財貨の値打ちの 「労働と費用」 への還元は、主として労苦としての労働の投入と財貨の値打ちとを、正義というイデオロギーを媒介に結びつけることとなった。これはアリストテレスには希薄であり、トマスに独自の把握であって、労働全収権論およびマルクスに継承されていく。[有江: 97]
……労働なり費用なりの支出には対応給付があるべきだ、という規範的な考え方……。簡単に言えば、労働には報酬が自明のように認められている,ということ…… [有江:91]
労働[labor] は 苦痛であるということ……。…… 労働は労苦であるが故に代償を得ることができる……。……労働自体がある行為を正義とする力を持っている…… [有江:92]
労働とその報酬との関係をものとものとの交換関係と同一視している……。ものとものとの関係の正義は等価交換であったから、労働とその報酬との関係でも等価交換が求められる。つまり、労苦としての労働という犠牲に対応した報酬が 「交換的正義」 の原理に則って考えられる。これは社会関係を考える上で、一つの理論的飛躍である。つまり、異なった労働による異なった財貨同士の交換取引において、ものとものとの関係と、人と人との関係が「交換的正義」という一つの原理によって関係づけられるからである。アリストテレスでは人格的序列に即した「分配的正義」と、形式的・量的均等による「是正的正義」の両面を持った「応報的正義」によって説明されていたところを、量的均等の「交換的正義」のみによって説明する……。いわば、社会の経済的諸関係を「交換的正義」という物象的な関係のみによって説明する……。 [有江:92]
財貨の値打ちの 「労働と費用」 への還元は、主として労苦としての労働の投入と財貨の値打ちとを、正義というイデオロギーを媒介に結びつけることとなった。これはアリストテレスには希薄であり、トマスに独自の把握であって、労働全収権論およびマルクスに継承されていく。[有江: 97]
〈抽象的個人の生成〉
具体的な経済行為の「交換的正義」による意味づけの一面化からは、逆に人々の人格的な価値序列は後景に退き労働の量や欲求の大きさが量的に相違するだけの、均質な人間類型把握がそこから浮かび上がってくる。[有江: 82]
生産された財貨の交換に際しても、 「労働と費用」 という生産の事情は当事者の地位や身分に関わりなく、匿名性において単に量的・形式的な問題として処理されることになる。これは、労働に本来は伴う人格に付随した事象が、労働と報酬との関係では問題とされなくなることを意味している。つまり、経済的関係の中においては、人々はその身分や出自を問われないただ抽象的個人として相互に対峙しあえばよいのである。[有江:92]
財貨がある尺度で等価であればよいということは、生産当事者の人格的種差を問うことなく、なんらかの供給条件の量的な差異のみが問題となる。したがって、交換取引の場に立ち現れるのはほとんど経済主体としての抽象的個人といってもよく、経済過程を通じてこそ人格的平等の端緒が形成されることが暗示される。[有江: 96-97]
生産された財貨の交換に際しても、 「労働と費用」 という生産の事情は当事者の地位や身分に関わりなく、匿名性において単に量的・形式的な問題として処理されることになる。これは、労働に本来は伴う人格に付随した事象が、労働と報酬との関係では問題とされなくなることを意味している。つまり、経済的関係の中においては、人々はその身分や出自を問われないただ抽象的個人として相互に対峙しあえばよいのである。[有江:92]
財貨がある尺度で等価であればよいということは、生産当事者の人格的種差を問うことなく、なんらかの供給条件の量的な差異のみが問題となる。したがって、交換取引の場に立ち現れるのはほとんど経済主体としての抽象的個人といってもよく、経済過程を通じてこそ人格的平等の端緒が形成されることが暗示される。[有江: 96-97]
6. メリトクラシーとの関係
三種の正義を用いて、メリトクラシーもしくはその克服について語るとしたらどうなるだろう?
わが国の代表的なアリストテレス研究者の一人である岩田靖夫は次のように述べている。
交換的正義の根底に 「能力に応じて取るのが正義である」 という思想がはっきりと顔をのぞかせている……。そこに配分的正義と通底する、或いはむしろ配分的正義を成立せしめている根本姿勢が見える……。[岩田 1985: 270]
岩田のこの解釈はむしろトマスにたいして妥当するように思われる。前項に紹介した有江の議論によれば、人と人との関係において成り立つのが分配的正義、モノとモノとの関係において成り立つのが是正的正義であった。そして、トマスは後者を拡張・一面化する交換的正義という一つの原理によって、人と人との関係とモノとモノとの関係を一括して処理することを主張した。上の引用文に述べられているのは、業績というモノを取引の一項とするいわば《物象的メリトクラシー》とみなすことができよう。
トマスとは異なり、アリストテレスは人の関係 (人格的価値序列) とモノの関係 (量的均等) とを区別したうえで、両者を組み合わせる応報的正義を語っている。彼は、この人格的価値の本質を、ポリスの秩序維持に関連づけづけたわけだが、そこに労働を代入すれば、共産主義の第一段階のイメージが導かれる(すなわち、〈労働量とモノとの等価交換 (算術的比例) 〉+〈社会への貢献度の差異に応じた対応給付 (幾何学的比例)〉=〈応報的正義〉)。仮にこれを《応報的メリトクラシー》と呼んでおく。
上の整理は、共産主義の第一段階にかんする前述の有江の評価に従ってみたものだが、この段階の 「形式的構造」 を 「『応報的正義』そのもの」 とみなす彼の理解にはやや疑問が残る。有江によれば、 「マルクスは、ここに残存する、貢献度の差異に応じた分配という理念に異議を唱えるのである」 [有江: 45] とされるが、マルクスが異を唱えたのは、正確には、 「人々がただ労働者としてのみ考察され、彼らのそれ以外の点には目を向けられず、ほかのことは一切無視される」 [マルクス『ゴータ綱領批判』] ということである。同量の労働が各個人にとって同じことを意味しないという平明な事実を無視するこの共産主義の第一段階が想定している人間は、抽象的人間であり、そのかぎりにおいて、 「彼らはまだモノとして存在している」 [カストリアディス: 344]。してみれば、そこに成立するのはむしろ《物象的メリトクラシー》ということになろう。後藤の言う 「メリトクラシーそのもの」 は、マルクス自身によって 「ブルジョア的平等」 にすぎないとされるこの平等のことであると解される。
では問題。今この世に存在しているのは、《応報的メリトクラシー》か《物象的メリトクラシー》かどちらなのか? 私見では《応報的メリトクラシー》である。トマスによって先駆的に示唆された《物象的メリトクラシー》は原則であり、実際はそれを大きく逸脱している。つまり、現実社会のなかでは、ブルジョア的原則に照らせばあってはならないはずの人格的価値序列が明らかに先行しており、そのもとではじめて等価交換がおこなわれている。それにたいして、共産主義の第一段階では 「もう原則と実際とが衝突することはない」 [マルクス] 。
分配的正義についてはどうかというと、アリストテレスの場合は、まさしく人格的価値のアリストクラシーである。先に、ルソーにかんして、彼の構想を 「真価の貴族制」 (《メリト・アリストクラシー》)とみる見解を紹介したが、なるほど、そのかぎりでは、彼はアリストテリアンであったわけである(この点につきすぐ後で触れる)。ただし、このアリストクラシーの形態は、何をもって社会にたいする貢献をもたらす人格特性であるとみなすのかに応じて可変的である。デッラ・ヴォルペの場合は、それは労働であり、そこからいささか奇妙に響くかもしれないが《アルバイト=メリト・クラシー》とでも呼ぶべきものが生まれる。念のためいっておくが、これと《応報的メリトクラシー》との決定的なちがいは(もしあるとすれば)そこに等労働量交換(算術的比例)が存在しないという点にある。
また、共産主義の第二段階においては、もちろん、労働に代えて必要もしくは欲求が置かれることになる。 「各人はその能力に応じて、各人にはその必要に応じて」 というテーゼについては次項で検討する。
それではここで、ルソーの見解をもう一度みておきたい。彼の構想については、これを《メリト・アリストクラシー》とみなすのが大筋では妥当であろうと思う。しかしながら、そこにはなお両義的な解釈の余地が残っている。それは、幾何学的比例を決定する人格的価値評価を誰がどのようにしておこなうのか、という点にかかわる。アリストテレスの場合は、既存のポリス秩序の維持という目的が先行しているので、この人格的価値序列はいわば所与であったが、ルソーの場合はそうはいかない。
先に述べたように、ルソーは、為政者に人格的価値評価を禁じる。ところが、分配的正義の要件としてこの評価は不可欠である。それは存在するのか? 存在する。それは 「人民[peuple]」 がくだす 「公共的評価 (estime publique) 」 によってもたらされるとされるが、にもかかわらず、ルソーは、 「市民たちの地位を個人の価値 (merite personnel) にもとづいて」 決定することを拒絶し、 「彼らが国家にたいしておこなう現実のサービス (services reels)、より正確な評価を受けられる現実のサービスにもとづいて」 決定すべきだと主張する [DI: 222-223]。 市民の地位を実際に分配するのが為政者であるし、また 「現実のサービス」 は 「個人の価値」 を反映しているだろうから、と考えると納得がいくような気もする。しかしながら、ここにはアリストテレスの分配的正義からの重大な逸脱が生じている。事前におこなわれるべき人格的価値序列の決定が、 「現実のサービス」 の評価という形で延期されてしまっているからである。さらに、多少の誤差はあるにしても人格的価値評価と近似的な 「現実のサービス」 の評価に応じる分配というこの考え方の背景には、明らかにルソーの労働賛美が認められ、またその考え方のなかには結果的に等労働量交換という発想が暗示されているように思われる。そうしてみると、交換的正義に代えて分配的正義をというルソーの意図とは裏腹に、この構想は《物象的メリトクラシー》に限りなく近づいていく。(もちろん、ルソーにとっての女性やアリストテレスにとっての奴隷は分配ゲームから排除されており、人格的価値序列化の対象外である。)
ルソーの議論の延長線上でまず第一に問われるべきは、おそらく、 「人民」 がくだすと想定されている 「公共的評価」 によって遂行される人格的評価のあり方であろう。言い換えれば,これはまさしく承認の問題であり、そこに登場してくるのは,労働を本質とする平等な抽象的個人ではなく、さまざまな身分、皮膚の色、性、能力等々をまとった具体的人間である。社会にたいする貢献といった一般的な基準に依拠することで満足すべきでないとするなら、これらの人格的属性をいわば直接に処理する手だてを考案しなければならないということになるだろう。
労働にかんしていえば、 「『労働こそ人間の本質』『労働することこそ全ての価値の源泉』といった『労働神話』は、『労働価値説』を可能にし『搾取』の概念を確立するなどの効用はあったものの」 [江原 1990: 222]、 もはや、その役割の大半は果たし終えたとみるべきではないのか。実際、 「労働価値論が説明の目的としている搾取について、より一般的な搾取概念を定立することによってその説明原理から逆に労働を排除する」 学的営みも進んでいる [有江: 351-355]。この新しい説明原理においては、当然のことながら、承認問題にかかわってさきほど挙げた種々のインデックスがしかるべき位置づけを与えられることになる。解放の物語が〈労働神話〉に依拠しているかぎりは、いかなる正義概念をもってきたとしても、結局のところ〈能力に応じて〉という隘路から抜け出ることはできないと考える。
7. アクシア問題
分配の正義が扱う人の値打ちを現実の行為に還元しないというスタンスをとるにさいしては、よほど慎重にかからないと、ルソーが懸念していたように 「為政者の勝手気儘」 がまかりとおることになってしまうだろう。この項では、このような 「勝手気儘」 に陥らず、なおかつ還元主義をも回避する、そのような術が果たしてありうるのかどうか、あるとすればどんな、というようなことを考えてみたい。
分配の正義は、交換の正義と対比されるとき、実質的な意味をもつ。すなわち、現実を批判的に理解しようとするさいの参照規準として機能しうる。しかし、オルタナティヴとしては、それはまだ空虚な形式にすぎない。なぜなら、アリストテレス自身が述べているように、 「アクシアに応じて」 というとき, 「万人が同じひとつのものをアクシアとみなしているのではなく、民主主義のひとは自由をアクシアとみなし、寡頭主義のひとは富を (或るひとびとは良い生まれを) 、貴族主義のひとは器量をアクシアとみなしている」 [NE: 1131a28-29] から。要するに、アクシアはブランクになっているのである。
したがって、分配の正義の基本問題は、アクシアに何を代入するかということになる。候補はいろいろ考えられる。たとえば、能力、功績、貢献、必要、欲求、適性、努力などなど。(用語法についてのお断り。〈アクシアαξια〉の訳語は `desert'、`worth'、`merit'、`value'、 「値打ち」 「真価」 「価値」 「原価値」 など多彩である。これらの訳語と代入候補となる指標との混同を避けるために、つまり、メリットにメリットを代入するとか、メリットにニーズを代入するといった紛らわしい表現を避けるために、アクシアはアクシアと表記することにする。)
この基本問題に関連して、さらにいくつかの問題が派生してくると想定される。たとえば、特定の一つの指標が、あらゆるケースにおいて妥当であるのか、それともケース・バイ・ケースに指標が異なるのか。また、同時に二つの指標を代入することは可能なのか。その場合には、両者のウェイト・バランスはどのようにして決まるのか。さらに、この代入の問題は、アリストテレスの例示にあるように、体制選択 (社会の構成原理の選択) 問題と不可分であるということは明白であるが、視点を逆転させてみるならば、既存の政治文化による被拘束性という問題ともからんでくる。
ところで、あるいは、アクシアとは個人の具体的全体性のことであり、あれこれの指標によってあらわされるものでもなければ、それらの指標の束でもないはずだ、との異議もありえよう (この場合には、アクシアはブランクどころか、中身の充満した具体的人格そのものとなる) 。しかしながら、それはそのとおりであるかもしれないが、そのように人格を文字通り丸ごと捕捉することは絶対に不可能であるし、たとえ可能だとしても、それを分配の基準として使うことはできないし、使ってはならない。そんなことをしたら、 「あなたは世界で何番目の人格ですよ」 [吉田],と宣告するに等しいからである。
ところで、分配の正義をめぐるこのような一連の問題群は,教育制度論の文脈においては、〈能力に応じて〉と〈必要に応じて〉というお馴染みの二つの原理の調停可能性の究明に深くかかわってくる。言うまでもなく、これは黒崎勲の理論の中心的課題であった。たとえば、かつては、 「二つの原理を、異なるレベルの教育制度にそれぞれ適用範囲を限定することによって統一的にとらえようとする」 [黒崎 1989: 189] と書かれていた。ところが、最近では、 「個人の要求により多くの比重を与え、個人の教育要求と社会的要請との関係を周期的にバランスさせようとする」 [黒崎 1995: 123] と言われ、 「個人の発達の必要と社会的要請とを統合する多様な教育理念」 [同: 192] が提唱されている。このちがいは、前者が教育システム内における二原理の調停問題を、後者が教育と経済という異なるシステム間の接合問題を主題化しているところから必然的にもたらされたものであろうと一応は理解することができる。
とはいえ、教育理念による多様化の意味するところが、 「能力の程度や尺度といったものによって多様化されるのではなく、自らの発達の必要にふさわしい教育理念を備えた教育の機会を保障されるべきであるということ」 [同: 187] だという断言を読むといささか戸惑いを覚える。この文章は、〈能力〉と〈必要〉の勝負は後者の圧倒的勝利に終わっているとも読めるし、また、両者の概念的レベルに差が想定されている (クマとドウブツの勝負) とも読める。二つの原理の調停問題がお払い箱になったとは想像できないので、第一の読み方は適切ではないだろう。とすれば、あとのほうの読み方が当たっているのだろうか。しかし、いつどのようにして〈必要〉が格上げされたのか分明でない。思うに、〈必要〉が二つあるのだ。クマと勝負するイノシシとしての〈必要〉と、ドウブツとしての〈必要〉が。そして、二つの原理のバランスという問題を問題として認知するかぎりは、おそらく、教育理念の多様化を説明するのに、〈必要〉の語を使うよりも。いっそのこと、デッラ・ヴォルペの言う 「真価」 (=社会的に承認されるべき当のもの) をそのまま使ったほうがよほどスッキリしたのではなかろうか。要するに、 「新しい多様化の理念」 とは、 「真価」 (デッラ・ヴォルペ) に応ずる教育を、ということなのだ。そして問題はその 「真価」 にある。これをアクシア問題と呼ぶことにしよう。
8. 分配者問題
唐突だが、ここでプルードンの所論をみておきたい。周知のように、彼は、マルクスとルソーとアリストテレスに敵対した。これまでの論脈にかかわらせていえば、彼は、分配の正義に反対して、交換の正義を主張した。
奴隷の主人は二倍の仕事をした奴隷に二倍のブランデーを約束することができる。これが専制の法則であり、隷従制の法則である。[『所有とは何か』]
もう権威なんぞはごめんである。つまりそれは絶対主義的な法律の代わりに自由な契約を、国家の裁定の代わりに自発的な取り引きを、主権的な分配の正義の代わりに公正な相互的正義を……ということである。繰り返しいうが、これこそ、私があえて完全な転換、自己転回、すなわち革命と呼ぶところのものではなかろうか。[『19世紀における革命の一般理念』]
人間がはじめて社会における秩序をつくろうとして考えだした形式は、家父長制または位階制的形式である。そして、この形式においてその原則は権威、その作用は政府であるといえる。正義は後になってこそ分配の正義と交換の正義に区別されるようになったけれども、最初のうちは第一の局面においてのみ、すなわち、一人の上位者が多くの下位者どもに対して、各人に帰属するものを分配するという局面においてのみ、彼らの前に立ち現れたのである。[同]
もう権威なんぞはごめんである。つまりそれは絶対主義的な法律の代わりに自由な契約を、国家の裁定の代わりに自発的な取り引きを、主権的な分配の正義の代わりに公正な相互的正義を……ということである。繰り返しいうが、これこそ、私があえて完全な転換、自己転回、すなわち革命と呼ぶところのものではなかろうか。[『19世紀における革命の一般理念』]
人間がはじめて社会における秩序をつくろうとして考えだした形式は、家父長制または位階制的形式である。そして、この形式においてその原則は権威、その作用は政府であるといえる。正義は後になってこそ分配の正義と交換の正義に区別されるようになったけれども、最初のうちは第一の局面においてのみ、すなわち、一人の上位者が多くの下位者どもに対して、各人に帰属するものを分配するという局面においてのみ、彼らの前に立ち現れたのである。[同]
山下正男によれば、「分配の正義でなく交換の正義を正義論の中心に据えたプルードンこそ、真の意味でのヨーロッパ的伝説を継承し発展させた人物であり、むしろマルクスの方こそが異端の思想家だ」 [山下: 17] とされる。プルードン=山下において分配の正義がこのように低く評価されるのはなぜか。分配の正義が被分配者のほかに、超越的な分配者の存在を想定するからである。「独裁者の存在を容認する」分配の正義に比べれば、交換の正義による社会革命は「きわめて健全で危険性の少いプログラム」 [山下: 27] と映るわけだ。
社会関係を構成する概念として、「交換関係」=「二者関係」と「配分関係」=「三者関係」とを定式化したのはジンメルとのこと [平井: 50]。 平井宜雄はそれらを次のように定義する。(なお、平井のいう「配分関係」には、被配分者の特性を考慮する「分配志向的平等」と、それを考慮せず、もっぱら配分される財のみに着目する「配分志向的平等」とが含まれる [平井: 107-108]。)
交換関係とは、相対立する二者の間のギブ・アンド・テイクの関係、すなわち、一方が他方に対してなした行為が、他方にとって一定の意味をもち、それについて他方の行為が期待されるという関係をさす。交換の対象は財のこともあれば負財のこともある。……これに対して、配分関係とは、稀少な財または不可避な負財が或る個人(配分決定者によって複数〔最小の単位としては2〕の個人〔被配分者〕)に分けられる関係を言う。1人の配分決定者と2人の被配分者とは、ギブ・アンド・テイクの関係ではなく、資源および権威をもつ上位・下位の関係にある。[平井:52]
問題は、分配 (「配分関係」) において、分配者 (「配分決定者」) が独裁者に転じることを回避することができるか否か、どうすれば回避することができるか、という点に絞られる (以下、分配者問題と呼ぶことにする) 。平井によれば、ここにおいて、手続的正義が「正義性基準」の一つとして登場する,とされる。
配分関係において、被配分者が配分決定者のなす決定のプロセスをコントロールできるような資源または財 (主張し、反論する機会がその例) を与えられかつその財が一般の『平等命題』をみたして配分されている場合に、手続的正義の要請をみたしていると言う。[平井: 109]
さて、分配の正義を主張する論者たちは、このプルードン問題をいかに処理しているのか。
ロールズの場合には〈純粋な手続的正義〉が、ルソーの場合には〈一般意志〉がこの要請を果たすべく構想されている。それにたいして、マルクスの場合には、生産力の増大によって産出される無限の富がプルードン問題を発生させないと想定されている (必要なものを好きなだけ手にすることができる)。
しかしながら、ロールズの議論には、この〈純粋な手続的正義〉の遂行場である〈オリジナル・ポジション〉の構成法にかんして、また、インセンティヴの処理にかんして、すでにさまざまな問題点が指摘されている。ルソーの〈一般意志〉の内容は、周知のように、多数決で定まると構想されており、コンドルセはそれを数学的に確証しようとしたわけだが、そこには今なお多くの究明されるべき論点が残されている [cf. Grofman and Feld: 1988]。 そして、マルクスの希望的観測を採用することはもはやできないだろう。
9. 分配対象問題
三つめは分配の対象にかかわる問題である。たとえば、ジョン・ロールズにあっては基本財、アマルティア・センにあっては潜在能力に焦点が当てられる。そのほか、ドゥオーキンによる、福利の平等か、資源の平等かという問題設定もしばしば論議の的となっている。そこには、教育制度論が踏まえるべき多様な背景的論点(政治哲学的な論点、テクニカルな論点、実行可能性についての論点など)が示されているが、ここではそれらには立ち入らない。その代わりに、こうした一連の理論的試みを 「分配パラダイム」 と規定したえで、 「分配にかかわる諸問題は、満足のいく正義のコンセプションにとって決定的に重要であるけれども、社会的正義を分配に還元してしまうのは誤りである」 [Young 1990: 15] とこれを批判するアイリス・マリオン・ヤングの議論を紹介するところから始めたい。
彼女の主張は序論の次の部分に的確に要約されている。
わたしはまず……社会的正義への二つのアプローチを区別することから始める。一つは、持つということに第一位性を付与するアプローチ、もう一つは為すということに第一位性を付与するアプローチである。現代の正義諸理論は、物質的財と社会的サーヴィスの所有に焦点を注ぐ分配パラダイムによって支配されている。しかしながら、この分配への焦点化は、制度的組織についての他の諸論点を曖昧にし、それと同時に、しばしば、特定の制度や実践を所与のものと仮定している。
分配的の正義理論のなかには、物質的財の分配を越える正義の諸論点を考慮に入れようと明示的に試みる理論もある。それらの理論は、分配パラダイムを拡張し、自尊、機会、権力、栄誉といった財をカヴァーしようとする。しかしながら、物質的財を越えて、権力や機会といった現象にまで分配概念を拡張しようとする試みからは、いくつかの深刻な概念的混乱がもたらされる。分配の論理は、非物質的な財を、識別可能 (identifiable) で別々の諸個人のあいだに一定のパターンで分配される識別可能なモノもしくはモノの束として取り扱う。さらに、分配パラダイムにおいて仮定されている抽象化、個人主義、パターン指向は、しばしば、支配と抑圧をめぐる諸論点を曖昧にしてしまう。これらの論点は、どちらかといえば、プロセス指向的で関係的な概念化を必要とする。
分配をめぐる諸論点はたしかに重要ではあるが、正義のスコープはそうした論点を越えて、政治的なものそのものへと、すなわち、制度的組織のアスペクトが集合的な意思決定に潜在的に服しているかぎりにおいてはそれらのアスペクトのすべてにまで拡がっている。わたしとしては、これらをカヴァーすることができるように分配を引き伸ばすのではなく、むしろ、分配概念は物質的財に限定されるべきであり、正義をめぐる他の重要なアスペクトは意思決定プロセス、社会的分業、文化を含んでいるのだ、と論じる。そして、抑圧と支配こそが不正義を概念化するための第一位的なタームであるべきだと論じる。[ibid.: 8-9]
分配的の正義理論のなかには、物質的財の分配を越える正義の諸論点を考慮に入れようと明示的に試みる理論もある。それらの理論は、分配パラダイムを拡張し、自尊、機会、権力、栄誉といった財をカヴァーしようとする。しかしながら、物質的財を越えて、権力や機会といった現象にまで分配概念を拡張しようとする試みからは、いくつかの深刻な概念的混乱がもたらされる。分配の論理は、非物質的な財を、識別可能 (identifiable) で別々の諸個人のあいだに一定のパターンで分配される識別可能なモノもしくはモノの束として取り扱う。さらに、分配パラダイムにおいて仮定されている抽象化、個人主義、パターン指向は、しばしば、支配と抑圧をめぐる諸論点を曖昧にしてしまう。これらの論点は、どちらかといえば、プロセス指向的で関係的な概念化を必要とする。
分配をめぐる諸論点はたしかに重要ではあるが、正義のスコープはそうした論点を越えて、政治的なものそのものへと、すなわち、制度的組織のアスペクトが集合的な意思決定に潜在的に服しているかぎりにおいてはそれらのアスペクトのすべてにまで拡がっている。わたしとしては、これらをカヴァーすることができるように分配を引き伸ばすのではなく、むしろ、分配概念は物質的財に限定されるべきであり、正義をめぐる他の重要なアスペクトは意思決定プロセス、社会的分業、文化を含んでいるのだ、と論じる。そして、抑圧と支配こそが不正義を概念化するための第一位的なタームであるべきだと論じる。[ibid.: 8-9]
以下では、上に挙げられている論点のうち、分配の論理の過剰拡張にたいする批判のみを検討することにする。ヤングの批判の根拠は、一言でいってしまえば、 「モノ」 と 「関係」 との区別に求められる。後者は 「計測可能な量ではない」 [ibid.: 24]。したがって、これらにまで分配の論理を拡張するならば、 「そのような適用は、モノとしてよりは、むしろ諸々の規則や関係の関数としてよりよく理解され去るような社会生活の諸側面を抽象化してしまう」 [ibid.: 25]ことになる。そのような 「社会生活の諸側面」 の一つに 「機会」 がある。これを例にとって、彼女の言わんとしているところを確認しておこう。
「機会が多いとか少ない (some people having “fewer" opportunities than others) 」 という言い回しに注意を促しつつ、彼女は次のように述べる。
「機会とは、所有の概念ではなく、能為化[enablement]の概念である。それは、持つというよりは為すということにかかわる。彼/彼女がものごとを為すことを制約されておらず、それらのものごとを為すこのを可能にする条件のもとでの生活を妨げられていなければ、その人は機会をもっている、ということになる。この意味において機会をもっているということは、しばしば、食物や衣服や道具や土地や機械といった物質的な所有物をもっているということを意味する。しかしながら、能為化されているとか制約されているということは、人の行為を司る諸々の規則や実践,特殊な社会的諸関係のコンテクストのなかで他者が人を取り扱うその取り扱い方、多種多様な行為と実践の合流によって産みだされるより幅広い構造的可能性、により直接的にかかわっている。機会を、それ自体所有されるモノとして語ることは無意味である。それゆえ、人々が機会をもっているかどうかに応じて社会的正義を評価することは、分配の結果を評価することだけではなく、レレヴァントな状況において諸個人を能為化したり制約したりする社会的構造を評価することを含んでいなければならない。[ibid.: 26]
ちなみに、これを教育の機会に適用するとこうなる。
教育機会を提供するということは、たしかに、特殊な物質的財 ─ 貨幣、建物、書籍、コンピュータなど ─ を配分するということを必然的に含むし、また、資源が多ければ多いほど、教育システムにおいて子どもたちに差し出される機会の幅が拡がる、と考えるだけの理由が存在する。しかし、教育は、まずもって、社会的諸関係の複雑なコンテクストのなかで起こる一つのプロセスである。合衆国の文化的コンテクストにおいて、男子と女子、労働者階級の子どもと中産階級の子ども、黒人の子どもと白人の子どもは、たとえ、等量の資源が彼らの教育に捧げられたとしても、等しく能為化的な教育機会をもっていないことがしばしばである。このことは、教育機会にとって分配がイレレヴァントであるということを示すものではなく、ただ、機会が分配よりも幅広いスコープをもっているということを示すだけだ。[ibid.: 26]
こうしたヤングの議論を前にしても、別に奇異の思いは湧いてこないだろう。ヤングは、 「分配パラダイム」 に潜んでいる存在論、すなわち、 「関係よりも実体のほうに一位性を付与するという社会的存在論」 [ibid.: 27]を批判しているのである。その批判は粗削りであり、さまざまな反論も可能であろうが、こと教育の場面を思い浮かべるとき、彼女の主張は重大な問題を提起するように思われる。
たとえば、教育の機会均等論は、クラス・サイズに関心を寄せる。これは、一人の教師に何人の生徒を割り当てるかという意味では、典型的な分配問題である。教師一人当たりの生徒数の問題は、逆にみれば、生徒一人当たりの教師数の問題である。教師一人当たりの生徒を30人にすべしという主張は、それはそれでいい。ところが、生徒一人当たりの教師を1/30人にせよ、というのは何だか変な感じがする。1/30人の教師っていったい何だ? しかし、これは荒唐無稽な想定ではない。少なくとも、それを真面目に論じている理論家がいる。クリストファー・ジェンクスがその人である。
ジェンクスは、教育の機会均等にかんする異なる5つの見解(民主主義的平等・道徳主義的平等・弱義の人間的正義・強義の人間的正義・功利主義)を検討するために、一つの仮想的ケース・スタディを試みている。
これら5つの教育の機会均等コンセプションの違いと、そしてそれぞれが解釈される仕方の違いをわかりやすく説明するために、わたしは、一つの具体例に焦点を絞ることにする。ある小さな町で、ある一人の教師 ─ ミズ・ヒギンズと呼ぶことにしよう ─ が教授する3年生の読み方の授業がそれである。われわれと同じように、彼女も平等な機会についてはこれを確信している。彼女の問題 ─ われわれの問題でもある ─ は、彼女が自由にできる主要な教育資源、すなわち彼女の時間と注意力の分配にかんして、平等の機会についての彼女の確信はいったい何を含意しているのか、ということである。[Jencks 1988: 518-519]
ヤングだったら 「ミスタ・ヒギンズの間違いなんじゃないの?」 と皮肉の一つも言ってやりたくなるところかもしれない。それはさておき、 「分配パラダイム」 とそれの前提している 「社会的存在論」 を自覚的に批判するヤングでなくても、このジェンクスのケース・スタディはトンでもないものと受け取られるにちがいない。それは教育という営みの特性を無視している、というのがわが国の教育界からの常識的反応だろう。たとえば、雑誌『教職課程』の次の文章は、そうした常識を代弁するものである。
子どもたちにとって、教師は大切な先生である。ところが往々にして、教師はそのことを忘れてしまう。ひとりの子どもは学級の中の子どもたちのひとりである。したがって、ひとりの子どもに向けられる注意は、学級の子どもの人数分の一ということになりがちである。ところが子どもはこうしたところを敏感に感じとる能力を自然に身につけているのである。/子どもたちはそれぞれ別々の個性をもった存在である。したがって、子どもたちの個性を尊重するならば、ひとりひとりをかけがえのない存在として捉えなくてはならない。こうした意識で子どもたちに接するならば、自分のもっている注意力の何分の一の注意を向けるという意識はなくなるはずである。[『教職課程』1996年11月号, 49]
稚拙な表現だと思われるかもしれない。なんなら、もっと洗練された言い回しに書き直そう。
優れた教育実践は多様な質を備えた生徒に対して、共同の場において働きかけることを可能にする〔。〕
教育活動の力量の向上〔は〕生徒の多様性を教育を豊かにするための契機として受け止めることを可能に〔する。〕
教育活動の力量の向上〔は〕生徒の多様性を教育を豊かにするための契機として受け止めることを可能に〔する。〕
どちらも黒崎『教育と不平等』からの引用である [黒崎 1989: 157, 158]。この場合には、教師が所有しており自由に処分できる稀少な注意力は、ヤング的な存在論的転回を経て、 「教育活動の力量」 という関係概念へと変容しているようにも見える。もっとも,その 「教育活動の力量」 の 「水準」 を問題視するかぎりにおいては [同: 158]、実体論的傾向を完全に免れているということはできないであろけれども。いずれにしても、これはひとつの 「契機」 であって、稀少な資源ではなく、したがって分配の対象となる財でもない。
わたしとしては、ヤングの主張に完全に同意するわけでも,ジェンクスの思考実験装置に嫌悪感を抱くわけでもないし、センのように、モノとヒトとの関係を内に含んだ 「機能」 「潜在能力」 を基盤にして社会的正義を構想する可能性も捨てたもんじゃないと思っている。ただ、分配の論理だけではやはり不十分であり、その限界を見定める必要性があるということについては確認しておきたい。
10. 比例性問題
分配の正義の定式を構成する各項にまつわる問題点を数え上げる作業の締めくくりとして、比例性問題を考察する。アリストテレスによれば、分配において 「『正』とは比例的ということであり、『不正』とはこれに反して比例背反的ということである」 (『ニコマコス倫理学』) 。ルソーによれば、 「人為的不平等は、それが自然的不平等と同じ比率で釣り合っていないときにはいつでも自然法に反しているということになる」 (『人間不平等起源論』) 。そして、黒崎によれば、 「能力主義の原理に批判的に対置される個人の社会的承認の主張は、諸個人の自然的差異と社会的不平等との比例的配分を求めるものである」 [黒崎 1995: 58]。ことほどさように言及される比例性とはなんぞや?
平等理論の教科書といってよい Douglas Rae et al. [1989] によれば、 「比例的平等は……通常は反平等主義のことだと考えられている」 [Rae et al.: 60]。山下正男 [1976] によれば、 「比例の思想」 とはまさしく 「階級の思想」 にほかならない。
社会心理学的な正義論の主流(?) である公平理論 (equity theory) は比例関係の成立している状態を公平と呼ぶ。すなわち、個人Aと個人Bが共同関係にあり、A、Bの得る結果をそれぞれOA、OB 、投入をIA、IB とするとき、 OA/IA=OB/IB ならば、この状態は公平であり、公平が破られた場合には、心理的に悩んだり、反省したり、開き直ったりするというわけである。
この公平理論にたいする批判の代表的なものがモートン・ドイッチュのそれである。平井宜雄の紹介文を引用しておく。
Deutchは、公平理論に対し、それが専ら経済的価値が支配する局面のみに考察を限定していると批判し、非経済的な社会関係におけるその妥当性を疑問視する。彼によれば、正義は個人の福利 (well-being) を増進するための効果的な社会的協力を育成する手段であり、経済的生産性が第一次目標であるような協力関係にあっては公平が正義の原則であるが、公平による配分は、羨望や優越感をひきおこしてこの目標を害するので、むしろ友好的な社会関係の育成維持が共通の目標である協力関係においては、必要 (need) (たとえば最貧者の生活維持の必要) が正義の原則となることを、実験や観察にもとづいて明らかにする。要するに、競争や非人格的な世界や、利益最大化が問題となる社会関係でのみ公平理論が妥当する、というのである (Deutsch 1975)。[平井: 98-99]
ドイッチュはこうした観点を教育の場面にも応用しており (“Education and Distributive Justice: Some Reflections on Grading Systems" in Deutch 1985 )、とても興味深い所見を呈示しているけれども、ここでは、このドイッチュの公平理論批判を、比例性原理の無限定な適用にたいする異議の一例として挙げるにとどめる。要するに、平等理論のなかで、比例性原理は必ずしも座りがよいわけではないのだ。
そのことを確認したうえで、今度は、比例性原理を平等原理の内に含めようとする試み、言い換えれば、 「階級の思想」 ではない 「比例の思想」 の可能性を追求しようとする試みを見てみよう。
センによれば、平等と比例性とは形式的に相いれない原理ではないと言う。
比例性原理といったタイプの規則には、しかるべく定義された分析的要件を具えた一種の形式的平等が含意されている。すなわち、このケースにおいては、中心的特性Xをともに同じだけもつ異なる(任意の)パーソンは、同じ価のYを受けるに値するとみなされなければならない。[Sen 1996: 397]
なるほど、これは平等な処遇ということの形式的表現である。しかし、問題は、その平等な処遇が 「持てるものにより多く」 という 「階級の思想」 と整合的だという点にあった。ここで注意しておくが、もちろん、 「能力に応じて」 ではなく 「必要に応じて」 とすれば 「階級の思想」 にはならないかもしれないが、ここで問題にしているのは、そのようなアクシア問題ではない。
センは、 「X1単位当たり等しい量のYを」 というのが厳密な意味での比例性原理であるということを認めたうえで、 「しかしながら」 と次のように続ける。
実際には、その名称にもかかわらず、いわゆる比例性原理を適用するさいには、比例性以外の単調関数 f(X) を考慮に入れるのが普通である。このことは、各自のXの値にたいして『与えられるべき』Yの値が『比例性』原理によっていかなる意味で決定されると想定されているのか、というその意味を特徴づけるためのスケール調整 (rescaling) という問題を追加する。[ibid.: 397]
どういうことか考えてみたい。
《2人の子どもをA、Bとする。テストで頑張れば頑張った分だけご褒美をあげると約束。原資は1000円。前回のテストの点数は、A: 40点、B: 60点。そして今回は、それぞれ50点、70点だった》とき、以下の4通りの処遇のうちからいずれかを選ぶとする。
- 得点1点を頑張り1単位とすれば、2人とも10単位となり、2人に 500円ずつ。
- 得点の伸び率1パーセントを頑張り1単位とすれば、Aは25単位、Bは17単位となり、A:595円、B:405円。
- 100点満点までの不足分をどれだけ縮めたかという率を頑張り1単位とすれば、Aは17単位、Bは25単位となり、A:405円、B:595円。
- 最大潜在能力(A: 80点、B:100点)までの不足分をどれだけ縮めたかという率を頑張り1単位とすれば、Aは25単位、Bは25単位となり、2人に 500円ずつ。
ケース(1)は、各人の能力も過去の努力も無視している。
ケース(2)は、過去の努力を等しいとみなしている=能力の差異を考慮している。
ケース(3)は、得点が高くなるほど、困難の度合いが増し、大きな努力が必要となると想定している。
ケース(4)は、ケース(3)の想定に加えて、能力差を考慮に入れている。
ケース(2)は、過去の努力を等しいとみなしている=能力の差異を考慮している。
ケース(3)は、得点が高くなるほど、困難の度合いが増し、大きな努力が必要となると想定している。
ケース(4)は、ケース(3)の想定に加えて、能力差を考慮に入れている。
このように、アクシアに 「頑張り」 を代入し、比例性原理を適用する場合であっても、さまざまなケースを考えることができる。それに応じて、結果状態は異なりうるし、また、結果状態が同じであっても、プロセスに違いがあったりもする。要するに、 「比例の思想」 は結果を一義的には決定しないということだ。 しかしながら、このこと(=平等な処遇が複数の形態をとりうるということ)の確認は、実質的議論の出発点にようやくたどりついたということを意味するにすぎない。問題は、平等な処遇はいかなる形態をとるべきなのか、ということである。その探究は、歴史的・文化的コンテクストのなかで、さまざまな経験的知見を駆使して進めるほかない。しかし……
11. 制度の問題
しかし、分配の正義にもとづく社会構想を、形式論理的に、あるいは経験科学的に導き出せると思い込むのは危険である。多くの論者が指摘しているように、そこには規範的問題が潜んでいるからだ。
規範的に重要な問いは、正義にかなった分配が比例的に平等であるのかどうかということではなく (なぜなら、それは明らかに比例的なのだから) 、分配にかんしてメリット [=アクシア: 田原] をいかにして測定するのかという問いである。そして、この後者の問いは、比例的平等という数学的観念が何も口出しできないような規範的問いである。[Westen 1990: 57]
この問いにたいする答えは、アリストテレス自身が認めているように、社会体制に応じて異なる。しかし、 「アクシアの定義や措定の問題にかんして、人々や諸党派やさまざまな国家社会 (cities) が相互に見解を異にし対立し」 ようとも、
ある意味で、所与の国家社会の内部において遂行されるどんな分配も、あえてかく表現すれば、事実上 (de facto)、正義にかなっているように見えることだろう。なぜなら、この分配は、当該国家社会が規準であり原価値であるとして措定/制度化したアクシアに必然的に対応するだろうから。[カストリアディス: 341]
であるがゆえに、なおのこと、
《誰が何をもつべきか?》という問いに決定的かつ根拠ある答え ─ 「正当化された」 答え ─ を出してはじめて (われわれにそれができたとしての話だが ?)、分配の正義、正義にかなう分配が存在する (または存在しうる ?) ということになろう。[同: 341]
この引用文のなかで、カストリアディスが疑問符つきの仮定法を挿入しているところからうかがわれるように、彼は、 「決定的かつ根拠ある答え」 を出すことができるかどうかについては懐疑的である。
マルクスの 「論理的」 「究極的」 解答の背後には、それ自体では正当化も理論化もできない特定の選択、アクシアの選択が、依然として横たわっている。そして、このアクシアそれ自体は、今度は、「欲求」 (彼のテロスにおいては 「労働への欲求」 を含む) としての人間にかんする特定の形而上学的テーゼに由来している。…… 彼 [=マルクス] は、この [欲求] という理念をどうすることもできない。欲求カテゴリーが用いられる必要があるときにはいつも、彼はそれを度外視せざるをえないのである。[同: 348、351]
なぜ 「できない」 のか? 長い引用になるが、カストリアディスの言に耳を傾けてみよう。
アリストテレスとマルクスを制約している真の 「歴史的限界」 ……は制度の問題である。伝統的思想は、社会的-歴史的なものを、どこか他の所から 「知られる」 ものには還元されえない存在様式として考慮することができない。彼らを 「限界づけ」 ているのはこの不可能性である。こうした不可能性は平凡な思想家の著作には現れない。つまり、これら平凡な思想家は、社会的-歴史的ものを何か他のもの( 「自然」 「構造」 「欲望」 など)に 「還元」 してしまう。限界は偉大な思想家の著作のなかにしか現れない。それは、まさしく、思想のアンティノミー、内的分裂というかたちで現れる。……
制度や社会的-歴史的なものの問題が伝統的思考の限界となるとして、それはなぜかといえば、この問題が 「純粋に理論的な」 地平に措定されるからであり、また、現にある制度を説明し理由づけようとする一方で、あるべき制度のための道理にかなった根拠づけをおこなおうとするからであり、そのかぎりにおいてである。だが、制度の問題は 「理論」 を越えている。制度を社会的-歴史的創造として、現にあるがままに考えるということは、伝統的な論理的-存在論的な枠組みを破壊することを要求する。別の社会制度を提案するということは、政治的プロジェクトや政治的目標にかんする事柄であり、これらはたしかに討議や議論に付されるが、何らかの種類の自然や理性……に 「基礎づけ」 られうるものではない。
この前線、この限界を横切るには、この 「凡庸さ」 を理解しなければならない。価値 ( 「経済的」 価値でさえも)平等、正義は、基礎づけされたり構築されたり (あるいは、マルクスが時として 「正義」 を破壊しようとするように、破壊されたり)することのできる 「概念」 ではない。これらは、ありうるかもしれない、またわれわれがそうであることを意志するような社会の制度に関係する政治的な理念/意味作用 (ideas/signification) である。そして、この制度は、いかなる自然的、論理的あるいは超越的な秩序にも投錨されない。人間は自由にも不自由にも、平等にも不平等にも生まれない。われわれは、人間が正義にかなう自律的な社会のなかで自由かつ平等であれ、と意志する (われわれ自身がそうであれと意志する) ─ これらの用語の意味が決定的に定義されるようなことはありえないだろうということ、理論がこの課題にたいして為しうる貢献はつねに根本的に限定されており、本質的に消極的であるということを承知のうえで。[同: 361-362]
制度や社会的-歴史的なものの問題が伝統的思考の限界となるとして、それはなぜかといえば、この問題が 「純粋に理論的な」 地平に措定されるからであり、また、現にある制度を説明し理由づけようとする一方で、あるべき制度のための道理にかなった根拠づけをおこなおうとするからであり、そのかぎりにおいてである。だが、制度の問題は 「理論」 を越えている。制度を社会的-歴史的創造として、現にあるがままに考えるということは、伝統的な論理的-存在論的な枠組みを破壊することを要求する。別の社会制度を提案するということは、政治的プロジェクトや政治的目標にかんする事柄であり、これらはたしかに討議や議論に付されるが、何らかの種類の自然や理性……に 「基礎づけ」 られうるものではない。
この前線、この限界を横切るには、この 「凡庸さ」 を理解しなければならない。価値 ( 「経済的」 価値でさえも)平等、正義は、基礎づけされたり構築されたり (あるいは、マルクスが時として 「正義」 を破壊しようとするように、破壊されたり)することのできる 「概念」 ではない。これらは、ありうるかもしれない、またわれわれがそうであることを意志するような社会の制度に関係する政治的な理念/意味作用 (ideas/signification) である。そして、この制度は、いかなる自然的、論理的あるいは超越的な秩序にも投錨されない。人間は自由にも不自由にも、平等にも不平等にも生まれない。われわれは、人間が正義にかなう自律的な社会のなかで自由かつ平等であれ、と意志する (われわれ自身がそうであれと意志する) ─ これらの用語の意味が決定的に定義されるようなことはありえないだろうということ、理論がこの課題にたいして為しうる貢献はつねに根本的に限定されており、本質的に消極的であるということを承知のうえで。[同: 361-362]
いささか過激で晦渋な物言いだが、わたしとしては次のように受けとめる。教育制度について 「こうでなければならない」 と言うとしても、理論的な推論だけからはそのような主張は生まれないし、理論にできるのは、せいぜいのところ、いわゆる理論的正当化の 「不整合、誤謬、神秘化」 [同: 362] を暴くという 「消極的」 な役割を果たすことくらいだ、ということなのだろう。
では、そうした理論の限界を越えたところにある制度の問題とはどういう問題なのだろうか? カストリアディスによれば、それは 「社会の協調を保つ (hold society together) 想念の意味作用 (imaginary signification) の問題であり、諸個人のパイデイア (paideia) の問題である」 [同: 362]。その先がどうなるのかはわたしにはよくわからない。いずれにしても、〈正当化される〉ということが、〈誰もリーズナブルには否定することができない〉=〈誰もが受け入れなければならない〉≠〈誰もが受け入れることができる〉ということだとするならば [cf. Scanlon 1982: 110; Nagel 1991: 36] 、この課題に 「積極的」 に貢献するには正当化以上のもの、少なくともそれ以外のものが求められる、ということか?
12. アリストテレス派社会民主主義?
カストリアディスによれば、アリストテレスとマルクスは伝統的思考の限界を画す制度の問題に到達していたという。この境界の向こう側では自由とか平等とか正義といった用語は 「決定的には定義されない」 けれども、にもかかわらず、否それゆえに、彼らは 「それ自体では正当化も理論化もできないアクシアの特定の選択」 をおこなう。そのうえで、あるべき社会制度を構想する。この構想の説得力は、消極的な理論的推論に由来するというよりは、むしろ、それがどの程度豊かで具体的なイメージを積極的に喚起することができるかに左右されることになろう。この点で、マルクスの共産主義社会のイメージは空想的にすぎ、今ではかえって無力感を誘い出しかねない。
アリストテレスのほうはどうかといえば、彼がどんな構想を提出しているかについてはあまり知られていない (少なくともわたしはよく知らない)。そこで以下、アリストテレス派社会民主主義を提唱し最近脚光を浴びつつあるマーサ・ヌスバウムのアリストテレス解釈を、彼女の論文 “Nature, Function, and Capability: Aristotle on Political Distribution" (1988) に即して見ておきたい (ヌスバウムの見解のエッセンスと彼女のプロフィールにつき、[川本 1995: 77-9, 43] を参照)。
(1) アリストテレスの分配構想
「どんな人にせよ、それにもとづけばもっとも善く行為し、幸福に生活しうるところの仕組みが最善の国制 (politeia) であるということは明らかである」 [アリストテレス『政治学』 Pol: 1324a23-25]。 すなわち政治的仕組みの評価は 「一人一人について、彼らがその仕組みによって最善に機能することができるようになっているかどうか」 [Nussbaum 1988: 147] に左右される。したがって、 「アリストテレスによれば、善き政治的仕組みについての理論は、善き人間生活についての理論を必要としており、またそれに依拠している」 [ibid.: 147]。つまり、政治的仕組みの 「最善さ (best-ness) 」 の規準が、人々の機能の最善さでなのであって、その逆ではない。この点をヌスバウムは強調する [ibid.: 148]。さらに、アリストテレスによれば、 「最善の政治的仕組みを適切に探究しようとする者は、まず、もっとも選択に値する生活 (the most choiceworthy life) が何であるかについて明確にしなければならない。というのは、もしかれが不明確であるならば、最善の政治的仕組みもまた不明確のままにとどまらざるをえないからである」 (Pol: 132a14-17)。すなわち、
政治的仕組みは、その人々 (われわれはこのグループがどのように定義されるのかにかんしてもっと多くのことを語る必要がある) にたいして、十分な善き人間生活に必要な諸条件を保証することを任務とする。それは、誰もが,善き人間生活を構成する仕方で(ただし上記の制約 [=〈状況によって許される最大限にまで〉と〈設計において可能な諸条件を考慮に入れて〉という二つの条件を指す: 田原] を被りつつ)機能することを選択しうるようなコンテクストを創造するということである。」 [Nussbaum 1988: 149]
(2) アリストテレスとロールズ
善についての説明を分配の仕組みのそれに先行させるというこの見解は、ロールズの正義論と対照的である。より正確にいえば、彼の議論は、この先後関係を完全に逆転させるというよりは、むしろ、基本善のリストが物語っているように、善についての理論を可能な限り 「希薄」 なものにとどめるというものである。この希薄性指向は、 「善く生きることについての見解に自律的な選択を各個人に残しておきたいとする彼の願望に動機づけられている」 [ibid.: 151]。
そこでヌスバウムは二つの問いを立てる [ibid.: 151]。(1)アリストテレスならば、ロールズの希薄理論をどのように批判するだろうか? (2) 分配原理の採択が 「より濃厚な」 理論に先行されるべきだと主張するとき、アリストテレスは選択の重要性を見逃してしまっているのか?
問(1)について。 「ロールズの理論は希薄すぎるのだ。彼のリストは真に『基本的な』アイテムを落としている。また、それは、真に基本的なアイテムとの関連においてはじめてその値打ちがわかるアイテムに、独立した意義を与えている」 [ibid.: 152]。ヌスバウムは、基本的なアイテムと道具的なアイテムとを区別する。多くもつほうが少なくもつようもつねに善いのは前者である。それにたいして、ロールズが基本善のリストに加えている富はそうした独立的な値打ちをもたない道具的な善である。
これら道具的な善にたいする正しい見方は、それらの善と人間活動との関係性のコンテクストのなかで、さまざまな状況において、それらがそうした活動をどのように促進もしくは妨害するのかを問うことである。そして、それをしかるべき位置に据えることが立法者の第一次的な責任であるようなもの、多くもちすぎることはできないが、多くもつほうが少なくもつよりもつねに善いようなもの、それはこれらの機能の基礎となるものである。そのような基礎として選ばれることができるものが、すぐれた機能、善くおこなうこと、善く生きること、これらのことを可能にする諸個人の潜在能力 (capabilities) である。[ibid.: 152]
問(2) について。この相違は重要だが、両者の 「不一致の程度を誇張しすぎないようにすることも大切である」 。なぜなら、 「選択と実践理性に余地を起こさないような善き生の構想については両者ともためらうことなくこれを退ける」 からである [ibid.: 152]。アリストテレスが異議を唱えるとすれば、それは、
選択を強調するロールズにたいしてではなく、選択の道具にすぎない諸々のアイテムが独立した値打ちをもっていると示唆しているロールズにたいしてであろう。さらにまた、われわれが人々にそれらをめぐって選択権を行使することができてほしいと思うようなさまざまな機能、派生的善に彼らなりを意味を与えることになるさまざまな機能について、それ以上詳しくは述べたがらないロールズにたいしてであろう。[ibid.: 153]
(3) アリストテレスとセン
上記 (2) から推察されるように、ヌスバウム的アリストテレスによるロールズ批判は、センによるそれとパラレルである。アリストテレス=ヌスバウム=センが目指しているものは、
「人々をある具体的な仕方で生活し活動しうるようにすることである。このようなアプローチは選択の価値を無視するものではない。なぜなら、われわれが目指すものは、人々がこうした仕方で選択することができるようにしてやることであり、たんに彼らにそのように行為することを押しつけることではないからである。このことは次のことを意味する。1われわれは、実際の機能という観点からではなく、潜在能力という観点からわれわれの目標を定義するだろう。2われわれが生活の各領域においてもっとも重視しなければならない潜在能力の一つは選択の潜在能力である。[ibid.: 153]
(4) アリストテレスと功利主義
「分配可能な財は、それだけで値打ちがあるものとしてではなく、人々のためにそれらの財が為すことのゆえに価値あるのだとする点において、アリストテレスは功利主義者に同意するだろう」 [ibid.: 154]。しかし、 「人々の主観的選好」 たる 「欲望」 の充足を規準とすることには彼は 「猛然と反対するだろう」 [ibid.] 。 そうではなく、ヌスバウムによれば、 「諸機能のリスト」 は 「実践的賢慮の人 (the person of practical reason) の選好という観点から規定される」 [ibid.] ことになる。
この 「実践的賢慮の人」 が遂行する 「熟慮的評価」 は 「倫理的客観性」 を帯びているとされる。言うまでもなく、この 「客観性」 は、近代批判の立場からは、その恣意的性格が指摘されることになり、他方で、その批判が批判者自身を〈宙吊り〉にしてしまうのだが、ヌスバウムは判断を停止させることなく突き進んでいく。結局のところ、事実上、彼女自身が 「実践的賢慮の人」 の役回りをある程度演じることになりそうなのだが、そのことについてはすぐ後で触れる。
「倫理的客観性」 は主観的な欲望充足を規準とする功利主義や、ある種の文化的差異を強調して現状を追認してしまう思考スタイルにたいして批判的威力を発揮する。たとえば、 「経験域が非常に制限されてきた人々」 は 「自分が知らない多くのオルタナティヴズを欲っすることがそもそもできない」 。ヌスバウムが引き合いに出している例をとれば、 「明らかに栄養失調から数々の疾患に苦しんでいるのに、自分たちは善くおこなっているのだという確信をしばしば表明する」 女性たちがそうである。こうした事態を前にして、
効用に基礎を置くアプローチを用いる場合には、われわれは、そうした人々は本当に善くおこなっているのだ、立法者はそれらの人々にたいしてそれ以上の責任を負わない、と結論せざるをえない。それにたいして、アリストテレス的アプローチは、彼らがどんな善い人間的機能を実際に遂行することができるのか、と問う。このアプローチのもう一つの長所は、それによって、われわれはそうした状況を批判することができるようになり、それらの人々にもっと多くが与えられなければならないと言うことができるようになるという点にある。[ibid.: 155]
(5) 目標としての潜在能力
ヌスバウムによれば、 「アリストテレス的立法者」 が追求すべき目標は 「潜在能力 (capabilities)」 である [ibid.: 160] 。彼女は、アリストテレスのテクストの解釈をつうじて、異なる二つの潜在能力を区別する。
一つは内的 (internal) なものである。適切な状況に置かれればよく選択しよく行為しうる立場にあるような知的および性格的な特性や身体を人々は発達させうる。この種の潜在能力を I-capability と呼び、それをさしあたり次のように定義しよう。
適切な状況が現前したら、ある人が行為 A を選択することができるように、ある時点 t においてオーガナイズされているならば、その場合にのみ、その人は t において機能 A を I-capable である。」 [ibid.]
適切な状況が現前したら、ある人が行為 A を選択することができるように、ある時点 t においてオーガナイズされているならば、その場合にのみ、その人は t において機能 A を I-capable である。」 [ibid.]
なお、この定義の 「力点は選択に」 あり [ibid.]、「 I-capabilities は教育によって発達する」 [ibid.: 161] とされる。
しかしながら、I-capability が 「現に在っても、その活性化のための諸条件を欠いているということがありうる」 がゆえに、そうした 「外的(external)諸条件にかんしても気を配る必要がある」 [ibid.: 162]。
この種の潜在能力を E-capability と呼ぶことにし、次のように定義する。
時点 t において、ある人が機能 A について I-capable であり、かつ、A の行使を妨害もしくは阻止するような状況が現に存在していないならば、その場合にのみ、その人は機能 A について E-capableである。[ibid.: 164]
時点 t において、ある人が機能 A について I-capable であり、かつ、A の行使を妨害もしくは阻止するような状況が現に存在していないならば、その場合にのみ、その人は機能 A について E-capableである。[ibid.: 164]
ところで、これら I- and E-cpabilities の分配を受ける受け手について、アリストテレスはどう考えているのか (周知のように彼は生来の奴隷と女性を排除している)。 ヌスバウムによれば、
そのような分配の受け手であるための必要条件は、当該諸機能を遂行しうる未発達の潜在能力を生まれつき保有しているものとする、ということである。すなわち、この潜在能力は、適切な教育と外的資源が与えられるならば、人が、時間が経てば、その機能について十全に capable になるというような capability のことである。…… これを基本的 (basic) 潜在能力と呼び、次のように定義することにしよう。
適切な訓練、時間、その他の道具的な必要条件が与えられるとして、ある人が機能 A のためにオーガナイズされる個人的器質 (individual constitution) を有しているならば、その場合にのみ、その人は機能 A について B-capable である。[ibid.: 166]
適切な訓練、時間、その他の道具的な必要条件が与えられるとして、ある人が機能 A のためにオーガナイズされる個人的器質 (individual constitution) を有しているならば、その場合にのみ、その人は機能 A について B-capable である。[ibid.: 166]
つまり、 「少年は将軍としての機能について、……胎児は見聴きするという機能について、ドングリは木になるということについて…… B-capableである」 [ibid.] ということになる。
(6) 笛吹きの例
アリストテレス的な分配の正義の適用例として、しかもそのメリトクラティックな性格を示す例としてしばしば引き合いに出されるのが『政治学』第3巻第12章の有名な笛吹きの例である。彼は、笛を分配するときには、生まれや見た目の美しさではなく、笛吹き術の優劣に応じて分配すべきだ、と述べている。要するに、 「分配の規準は遂行されるべき機能にレレヴァントでなければならない」 [ibid.:167]。
この例は、I-capability から E-capability へと進むために必要な諸条件の割り当てにかかわっている。すなわち、優れたパフォーマンスを示した者に、笛吹きで身を立てることができるように素晴らしい笛を与える、という例である。しかしながら、ヌスバウムによると、 「彼 [=アリストテレス] は明白に,より一般的なポイントを指摘するためにこの例を用いている。すなわち、その capability は、他の諸特徴とは異なり、ある機能の遂行にとってレレヴァンスを有しているがゆえに、その機能のための諸条件の分配にとってレレヴァントな規準となるのだ」 [ibid.] とされる。したがって、すでに訓練済みの潜在能力に応じて、となるとは限らない。たとえば、I-capbility の必要条件 (教育 ! ) を分配するときには、B-capability を有しているか否かが決定的となる。この場合には、 「『根っからの奴隷』に理性的教育を与えてはならないが、しかし、B-capability を有している者にたいしては、その者の B-capability を E-capability へと成長を促すために必要とされるだけのレレヴァントな善・財を与えよ」 [ibid.] となる。
ここでは、分配の正義にかかわってすでに挙げた4つの問題に加えて5番目の問題、被分配資格問題が語られている。要するに、 「彼 [=アリストテレス] は、あらゆる capabilities について……それらの capabilities を活性化すべく準備するために必要ないかなるものをも要求する条件とみなしている」 [ibid. 168] 。したがって、どんな機能を遂行するためのどんな潜在能力が問題となるのかに応じて、その分配はメリトクラティックになったりならなかったりする。メリトクラティックな分配が主張されるのは多くの場合、政治的機能遂行というコンテクストにおいてである。しかし、 「倫理的および知的な I-capabilities の形成というコンテクストにおいては、彼はけっしてそのようには語っていない」 [ibid.] 。
(7) 必要としての B-capability
ところで、`capabilities' という述語を日本語に訳せば 「潜在能力」 ということになるだろうが、立法者が分配にさいして 「意を注ぐべき個人的特性」 が 「当該機能を遂行しうる B-capability の存在 (presence)」 であり [ibid.: 167] 、 「その目標がたんに財をバラ蒔くだけではなく、E-capabilities をうみだすことにある」 [ibid.: 168]とするならば、 「 B-capabilities は機能遂行に向けての必要 (needs for functioning) である」 [ibid.: 169] と解釈されよう。すなわち、
それら [=B-capabilities] は、それらがそこにあり、不完全な実現の状態にあるがゆえに、ひとつの要求・主張 (claim) を引き起こすのである。それらはある一定の活動様式へと伸びており、その活動様式の充足を要求する。もしもその活動が起こらなければ、それらは遮られているのであり、実を結んでいないのであり、不完全なのである。[ibid.: 169]
この 「潜在能力発達のための潜在能力的基礎 (the capability basis for capability development) 」 という考え方は、 「機能することがまだできない人々に注意を払うべし」 、 「エクセレントな functioning を最大化するよう努めるよりは、彼らすべてに注意を払わねばならぬ」 という立法者の任務を説明するための有力な基礎を提供する [ibid.: 169-170]。
(8) さまざまな問題と展望
こうしたアリストテレス的アプローチにもとづく作業は、ヌスバウム自身が認めているように、まだ 「緒についたばかり」 であり、さまざまな反問が予想される。 「 capabilities ( I にしろ E にしろ) を分配するとは何を意味するのか?」 「手段と条件へのどのくらいの、どんな種類のアクセスがあれば、十分であるとみなされるのか?」 「ある人がある機能について B-capable であるか否かを判断する場合に、どんな種類のレベルをわれわれは捜し求めているのか?」 「善についての相対的に濃厚な説明をもって operatingするとき、また、これを (たとえば)公教育システムをつうじて実行に移すとき、たとえ選択と実践理性を強調しようとも、われわれは、子どもたちが後になってからおこなうかもしれない多くの選択を不可能にしてしまうような仕方で最初から everyone にたいして何かを押しつけることになりはしないか? そして、このことは、道徳的に価値ある種類の ─ 人間がそれについて capable であることがもっとも欲されるような種類の ─ 選択の縮小であるのか否か?」 などなど [ibid.: 173-174]
ここでは、ヌスバウムが 「もっとも急を要する」 「是非とも解決されなければならない」 とする問題に的を絞る。そしてこの問題は、本ノートのこれまでの論脈に照らしても興味深い問題である。すなわち、 「都市 [=政治的社会のこと: 田原] がかかわるべき機能 (functionings) は何であるのか、またわれわれはいかにしてこのリストを得ることができるのか?」 [ibid.: 174]
ヌスバウムによれば、このリストは 「一方において非超然的 (non-detached) であるが、他方では客観的なものである」 [ibid.] とされる。
「非超然的」 とは、リストアップの作業は、 「人間の経験と選択から全面的に超然としている存在」 によっては遂行されえないということ、その作業は 「ある種の価値中立的な科学的事実を発見しようとする」 こととは違うということ、善く生きるということにとって 「何がもっとも重要なのか、真に人間的とみなすに十分なほど豊かでありそうな生の本質的部分は何なのかを自問する」 ということを意味する [ibid.: 175]。
「客観的」 とは、特定の文化や集団や個人が 「レレヴァントな人間的機能」 としてリストアップした機能をそのままでは 「客観的」 とはみなさないということである。なぜなら、 「もしもそうしてしまえば、欲望や選好を越えて潜在能力に着目することの意義の多くが失われてしまう」 からである [ibid.: 175]。“feel good and are doing well" と答えるインドの貧困地方の虐げられた女性たちを例にとりつつ、ヌスバウムは、 「差別と不公平に取り囲まれてしまっているなかで育てられた人々によって実際におこなわれる機能評価を批判する力をもつような客観的な評価手続きを明確にする」 ことができなければならないと主張する [ibid.: 175]。
「実際に生きられている人間の社会生活にとってまったく疎遠であるようなパースペクティヴを輸入しない」 という意味で 「非外部的」 でありつつも、依然として上のような意味で 「客観的である ─ そして、文化的な相対性にたいするある種の敏感さの入る余地がなお残されているという意味でも客観的である」 [ibid.: 176]、そんな冴えたやりかた!? 「われわれは、機能をめぐる問いにたいして、すべての人間のための一般的答えを、すなわち、文化的な差異の諸問題に不感症でもなく、なおかつ、不正義な文化を批判する方途をわれわれに与えてくれるような、そんな一般的答えを得ることができるだろうか?」 [ibid.: 177]。この問いにヌスバウムは肯定的に答える。
アリストテレス=ヌスバウムの手順はこうである [ibid.: 177-178]。 「あらゆる人間社会に共通すると思われるある一定の完全に一般的な諸条件を検討することから始める」 。たとえば、 「われわれは死を免れない」 等々という 「問題エリア」 のリストが確認される。次に、各々の問題エリアにかんして善き機能とは何かが問われ、 「徳もしくはエクセレンスのリスト」 がもたらされる。 「われわれは死を免れない」 という問題エリアにおいては 「勇気」 がそれに相当する。さらに、各々のエクセレンスは 「地についた問題 (grounding problem) 、 すなわち経験の圏域に照らしつつ明細化 (specified) される」 。このとき、その明細化された善き機能は多様でありうる。
このように歩を進めていくならば、第一に、われわれは、たとえば、勇気についていくつかの競合する説明を得つつもなお、一つのことを探究しており、そのことにかんして議論しているのだと納得することができる。そして第二に、さらにわれわれは、ある特定の善き機能がいくつかの異なる具体的な文化的実現形態を有しているということを発見しつつもなお、ここには単一の機能が存在しているわけではないと結論づけないでいることができる。それから、もし欲するならば、異なる実現形態の比較評価に向かうことができる。[ibid.: 178]
これが彼女の言うところの 「濃厚で曖昧な善のコンセプション (the thick vague conception of the good) 」 である。
アリストテレス派は、ロールズの『希薄理論』のように『希薄な』、すなわち、善く生きるための万能手段の列挙に限定された善のコンセプションではなく、『濃厚な』,すなわち、人間として生きることの全領域にわたる人間的な諸目的を扱う善のコンセプションを用いる。しかしながら、このコンセプションは、いい意味で曖昧である。すなわち、それは、具体的内容を細かく記述できる余地を十分に残していながらも、しかもなお、アリストテレスがそうしているように、善き生の『大まかな輪郭 (outline sketch) を描くのである。[Nussbaum 1990: 217]
長々と紹介してきたが、相対主義の誘惑にたいするヌスバウムの毅然とした態度、センと歩調を合わせつつも相対的に独自に深められた潜在能力アプローチ、 「希薄で明快な善のコンセプション」 にたいするオルタナティヴとしての 「濃厚で曖昧な善のコンセプション」 、これらから学ぶべきことはたくさんある。〈分配の正義 再論〉と題したこの項の冒頭に記したこととかかわらせていえば、 「人の値打ちを現実の行為に還元しないというスタンス」 にとって、潜在能力アプローチは有力な基礎を提供してくれる可能性がある。また、 「為政者の勝手気儘」 を回避するという要請にたいしては、 「〈人間であるとはどんなことかを仲間と異邦人たち相手に説明する物語〉を基盤」 として、 「科学的知性というよりもむしろ物語的な想像力 (story-telling imagination) を利用する」 [川本 1995: 78] ヌスバウムのやり方が一つの解答を示してくれているのかもしれない。とはいえ、焦れったいけれども、今のところは 「可能性がある」 とか 「かもしれない」 としか言えない。
なお、アリストテレス=ヌスバウムにおいて、選択がとりわけ重視されているということは注目に値する。ヌスバウムは、さまざまな人間的諸機能のすべてが 「何か重要なものを共通に有している」 [Nussbaum 1988: 179] と言う。そして、この 「人間的生はこうあるべしと考える何か」 とは 「『選択する』という働き、すなわち選択と実践理性の行使の内に暗示されている」 [ibid.: 180] とされる。すなわち、選択の位置づけは二重である。それは、善き機能を遂行するための条件であるとともに、それ自体が目標でもある。
-----------------------------------------------
【文献】 日本語: 50音順/外国語: ABC順
有江大介 1990:『労働と正義 ─ その経済学史的検討 ─ 』創風社.
アルカーロ,M. 1993:「不平等の問題 ─ イタリアにおけるルソーとマルクス主義にかんする論争の経過 ─ 」 (中島康予訳) 『中央大学社会科学研究所研究報告』第12号.
岩田靖夫 1985:『アリストテレスの倫理思想』岩波書店.
江原由美子 1990:「フェミニストは『労働』がお好き?」 『現代思想』 18巻, 4号.
川本隆史 1995:『現代倫理学の冒険 ─ 社会理論のネットワーキングへ ─ 』創文社.
『教職課程』1996年11月号
黒崎勲 1989:『教育と不平等 ─ 現代アメリカ教育制度研究 ─ 』新曜社.
黒崎勲 1994:『学校選択と学校参加 ─ アメリカ教育改革の実験に学ぶ ─ 』東京大学出版会.
黒崎勲 1995:『現代日本の教育と能力主義 ─ 共通教育から新しい多様化へ ─ 』岩波書店.
後藤道夫 1987: 「『共産主義』理念の再検討」 藤田勇編『権威主義的秩序と国家』東京大学出版会.
平井宜雄 1995:『法政策学〔第2版〕』有斐閣.
プルードン 1971:『所有とは何か』 (長谷川進訳) . アナキズム叢書『プルードンⅢ』三一書房, 1971.
プルードン 1971:『十九世紀における革命の一般理念』 (陸井四郎・本田烈訳) . アナキズム叢書『プルードンⅠ』三一書房.
マルクス『ゴータ綱領批判』大月書店 (国民文庫).
マルクス・エンゲルス『ドイツ・イデオロギー』『マルクス・エンゲルス全集』第3巻, 大月書店.
山下正男 1976:「比例の思想」 と 「階級の思想」 『現代数学』 第9巻, 第2号.
山下正男 1984:「正義と権利 ─ 西欧的価値観の歴史」 上山春平編『国家と価値』京都大学人文科学研究所.
吉田脩「選抜 ─ 試験は無難な方法」『朝日新聞』1991年10月9日.
Aristotle [NE] : The Nicomachean Ethics, tr. by H. Rackham, The Loeb Classical Library, 73, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1934. 加藤信朗訳『アリストテレス全集13 ニコマコス倫理学』岩波書店, 1973.
Aristotle [Pol] : Politics, tr. by H. Rackham, The Loeb Classical Library, 264, Cambridge, Mass.: Harvard UniversityPress, 1932. 山本光雄訳『政治学』岩波文庫, 1961.
Castoriadis, Cornelius 1975: “Valeur, egalite, justice, polit ique: de Marx a Aristote et d'Aristote a nous", in Textures, nos.12-13. 宇京頼三訳 「価値, 平等, 正義, 政治 ─ マルクスからアリストテレスとアリストテレスから我々まで」『迷宮の岐路〈迷宮の岐路Ⅰ〉』 法政大学出版局, 1994,所収.
CC ⇒ Rousseau 1765
Colletti, Lucio 1975: Ideologia e societa, Roma: Editori Laterza.
Com. ⇒ Thomas Aquinas
Connolly, William E. 1991: Identity/Difference: Democratic Negotiations of Political Paradox, Ithaca and London: Cornell University Press.
CS ⇒ Rousseau 1762
Delaporte, Andre 1987: L'idee d'egalite en France au XVIIIe siecle, Paris: Presses Universitaires de France.
della Volpe, Galvano 1964 [RM] : Rousseau e Marx e altri saggi di critica materialistika, 4 edizione, Roma: Editori Riuniti. 竹内良知訳『ルソーとマルクス』合同出版, 1968.
Deutsch, Morton 1975: “Equity, Equality and Need: What Determines Which Value Will Be Used as the Basis of Distributive Justice?", in Journal of Social Issues, 31.
Deutsch, Morton 1985: Distributive Justice: A Social-Psychological Perspective, New Haven and London: Yale University Press.
DI ⇒ Rousseau 1755
Dworkin, Ronald, 1978: “Liberalism", in his A Matter of Principle, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1985.
EP ⇒ Rousseau 1755
Fraser, Nancy 1992: “Rethinking the Public Sphere: A Contribution to the Critique of Actually Existing Democracy", in Habermas and the Public Sphere, ed. by Craig Calhoun,Cambridge, Mass.: The MIT Press.
Fraser, Nancy 1995: “From Redistribution to Recognition? Dilemmas of Justice in a `Post-Socialist' Age", in New Left Review, No.212.
Galliani, Renato 1989: Rousseau, le luxe et l'ideologie nobiliaire: etude socio-historique, Oxford: The Voltaire Foundation.
Giroux, Henry A. 1993: Living Dangerously: Multiculturalism and the Politics of Difference, New York: Peter Lang.
GP ⇒ Rousseau 1772
Grofman, Bernard. and Feld, Scott L. 1998: “Rousseau's General Will: A Condorcetian Perspective", in American Political Science Review, Vol.82, No.2.
Honneth, Axel 1992: Kampf um Anerkennung. Zur moralischen Grammatik sozialer Konflikte, Frankfurt/M: Suhrkamp.
Hulliung, Mark 1994: Autocritique of Enlightenment: Rousseau and Philosophes, Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
Jencks, Cristopher 1988: “Whom Must We Treat Equally for Edu cational Opportunity to Be Equal?", Ethics, Vol.98.
Kymlicka, Will 1989: Liberalism, Community and Culture, Oxford: Oxford University Press.
Masters, Roger D. and Kelly, Christopher 1992: “Editors' Notes to Second Discourse", in The Collected Writings of Rousseau, Vol.3, Hanover, NH: University Press of New England.
Nagel, Thomas 1991: Equality and Partiality, Oxford: Oxford University Press.
NE ⇒ Aristotle
Nussbaum, Martha 1988: “Nature, Function, and Capability: Aristotle on Political Distribution", in Oxford Studies in Ancient Philosophy (1988), Supplementary Volume.
Nussbaum, Martha 1990: “Aristotelian Social Democracy", in R. Bruce Douglass, Henry S. Ricahrdson, and Gerald M. Mara, eds., Liberalism and Goods, New York and London:Routledge.
PN ⇒ Rousseau 1753
Pol ⇒ Aristotle
Rae, Douglas, et al. 1989: Equalities, Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
RM ⇒ della Volpe 1964
Rousseau, Jean-Jacques 1753 [PN] : “Preface de Narcisse", OEuvres completes, Ⅱ, Paris, Gallimard, 1964. 佐々木康之訳 「ナルシス まえがき」 『ルソー全集』 第11巻,白水社,1980.
Rousseau, Jean-Jacques 1755 [DI] : Discours sur l'origine et les fondaments de l'inegalite parmi les hommes, OEuvres completes, Ⅲ, Paris, Gallimard, 1964. 本田喜代治・平岡昇訳『人間不平等起源論』岩波文庫, 1972.
Rousseau, Jean-Jacques 1755 [EP] : Discours sur l'economie politique, OEuvres completes, Ⅲ, Paris, Gallimard,1964. 河野健二訳『政治経済論』岩波文庫, 1951.
Rousseau, Jean-Jacques 1762 [CS] : Du contract social ou principles du droit politique, OEuvres completes, Ⅲ, Paris, Gallimard, 1964. 桑原武夫・前川貞次郎訳『社会契約論』岩波文庫, 1954.
Rousseau, Jean-Jacques 1765 [CC] : Projet de constitution pour la Corse, OEuvres completes, Ⅲ, Paris, Gallimard,1964. 遅塚忠躬訳『コルシカ憲法草案』『ルソー全集』第5巻,白水社,1979.
Rousseau, Jean-Jacques 1772 [GP] : Considerations sur le gouvernment de Pologne, OEuvres completes, Ⅲ, Paris, Gallimard, 1964. 永見文雄訳『ポーランド統治論』『ルソー全集』第5巻,白水社,1979.
Scanlon, Thomas M. 1982: “Contractualism and Utilitarianism", in Amartya Sen and Bernard Williams, eds., Utilitarianism and Beyond, Cambridge: Cambridge University Press.
Sen, Amartya 1996: “On the Status of Equality", in Political Theory, Vol.24, 1996,No.3.
S.T. ⇒ Thomas Aquinas
Thomas Aquinas [CN] : St. Thomas Aquinas Commentary on the Nicomachean Ethics, tr. C. I. Litzinger, Library of Living Catholic Thought, Vol.1, Chicago: Henry Regnery Com., 1964.
Thomas Aquinas [ST] : St. Thomas Aquinas Summa Theologia, Latin Text and English translation, Notes, Appendices and Glossaries, London and New York: Blackfriars, 1964-1975.
Trachtenberg, Zev M. 1993: Making Citizens: Rousseau's Political Theory of Culture, London and New York: Routledge.
Young, Iris Marion 1990: Justice and the Plitics of Difference, Princeton, NJ: Princeton University Press.
Walzer, Michael 1983: Spheres of Justice: A Defense of Pluralism and Equality, New York: Basic Books.
Westen, Peter 1990: Speaking of Equality: An Analysis of the Rhetorical Force of 'Equality' in Moral and Legal Discourse, Princeton, N.J.: Princeton University Press.
有江大介 1990:『労働と正義 ─ その経済学史的検討 ─ 』創風社.
アルカーロ,M. 1993:「不平等の問題 ─ イタリアにおけるルソーとマルクス主義にかんする論争の経過 ─ 」 (中島康予訳) 『中央大学社会科学研究所研究報告』第12号.
岩田靖夫 1985:『アリストテレスの倫理思想』岩波書店.
江原由美子 1990:「フェミニストは『労働』がお好き?」 『現代思想』 18巻, 4号.
川本隆史 1995:『現代倫理学の冒険 ─ 社会理論のネットワーキングへ ─ 』創文社.
『教職課程』1996年11月号
黒崎勲 1989:『教育と不平等 ─ 現代アメリカ教育制度研究 ─ 』新曜社.
黒崎勲 1994:『学校選択と学校参加 ─ アメリカ教育改革の実験に学ぶ ─ 』東京大学出版会.
黒崎勲 1995:『現代日本の教育と能力主義 ─ 共通教育から新しい多様化へ ─ 』岩波書店.
後藤道夫 1987: 「『共産主義』理念の再検討」 藤田勇編『権威主義的秩序と国家』東京大学出版会.
平井宜雄 1995:『法政策学〔第2版〕』有斐閣.
プルードン 1971:『所有とは何か』 (長谷川進訳) . アナキズム叢書『プルードンⅢ』三一書房, 1971.
プルードン 1971:『十九世紀における革命の一般理念』 (陸井四郎・本田烈訳) . アナキズム叢書『プルードンⅠ』三一書房.
マルクス『ゴータ綱領批判』大月書店 (国民文庫).
マルクス・エンゲルス『ドイツ・イデオロギー』『マルクス・エンゲルス全集』第3巻, 大月書店.
山下正男 1976:「比例の思想」 と 「階級の思想」 『現代数学』 第9巻, 第2号.
山下正男 1984:「正義と権利 ─ 西欧的価値観の歴史」 上山春平編『国家と価値』京都大学人文科学研究所.
吉田脩「選抜 ─ 試験は無難な方法」『朝日新聞』1991年10月9日.
Aristotle [NE] : The Nicomachean Ethics, tr. by H. Rackham, The Loeb Classical Library, 73, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1934. 加藤信朗訳『アリストテレス全集13 ニコマコス倫理学』岩波書店, 1973.
Aristotle [Pol] : Politics, tr. by H. Rackham, The Loeb Classical Library, 264, Cambridge, Mass.: Harvard UniversityPress, 1932. 山本光雄訳『政治学』岩波文庫, 1961.
Castoriadis, Cornelius 1975: “Valeur, egalite, justice, polit ique: de Marx a Aristote et d'Aristote a nous", in Textures, nos.12-13. 宇京頼三訳 「価値, 平等, 正義, 政治 ─ マルクスからアリストテレスとアリストテレスから我々まで」『迷宮の岐路〈迷宮の岐路Ⅰ〉』 法政大学出版局, 1994,所収.
CC ⇒ Rousseau 1765
Colletti, Lucio 1975: Ideologia e societa, Roma: Editori Laterza.
Com. ⇒ Thomas Aquinas
Connolly, William E. 1991: Identity/Difference: Democratic Negotiations of Political Paradox, Ithaca and London: Cornell University Press.
CS ⇒ Rousseau 1762
Delaporte, Andre 1987: L'idee d'egalite en France au XVIIIe siecle, Paris: Presses Universitaires de France.
della Volpe, Galvano 1964 [RM] : Rousseau e Marx e altri saggi di critica materialistika, 4 edizione, Roma: Editori Riuniti. 竹内良知訳『ルソーとマルクス』合同出版, 1968.
Deutsch, Morton 1975: “Equity, Equality and Need: What Determines Which Value Will Be Used as the Basis of Distributive Justice?", in Journal of Social Issues, 31.
Deutsch, Morton 1985: Distributive Justice: A Social-Psychological Perspective, New Haven and London: Yale University Press.
DI ⇒ Rousseau 1755
Dworkin, Ronald, 1978: “Liberalism", in his A Matter of Principle, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1985.
EP ⇒ Rousseau 1755
Fraser, Nancy 1992: “Rethinking the Public Sphere: A Contribution to the Critique of Actually Existing Democracy", in Habermas and the Public Sphere, ed. by Craig Calhoun,Cambridge, Mass.: The MIT Press.
Fraser, Nancy 1995: “From Redistribution to Recognition? Dilemmas of Justice in a `Post-Socialist' Age", in New Left Review, No.212.
Galliani, Renato 1989: Rousseau, le luxe et l'ideologie nobiliaire: etude socio-historique, Oxford: The Voltaire Foundation.
Giroux, Henry A. 1993: Living Dangerously: Multiculturalism and the Politics of Difference, New York: Peter Lang.
GP ⇒ Rousseau 1772
Grofman, Bernard. and Feld, Scott L. 1998: “Rousseau's General Will: A Condorcetian Perspective", in American Political Science Review, Vol.82, No.2.
Honneth, Axel 1992: Kampf um Anerkennung. Zur moralischen Grammatik sozialer Konflikte, Frankfurt/M: Suhrkamp.
Hulliung, Mark 1994: Autocritique of Enlightenment: Rousseau and Philosophes, Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
Jencks, Cristopher 1988: “Whom Must We Treat Equally for Edu cational Opportunity to Be Equal?", Ethics, Vol.98.
Kymlicka, Will 1989: Liberalism, Community and Culture, Oxford: Oxford University Press.
Masters, Roger D. and Kelly, Christopher 1992: “Editors' Notes to Second Discourse", in The Collected Writings of Rousseau, Vol.3, Hanover, NH: University Press of New England.
Nagel, Thomas 1991: Equality and Partiality, Oxford: Oxford University Press.
NE ⇒ Aristotle
Nussbaum, Martha 1988: “Nature, Function, and Capability: Aristotle on Political Distribution", in Oxford Studies in Ancient Philosophy (1988), Supplementary Volume.
Nussbaum, Martha 1990: “Aristotelian Social Democracy", in R. Bruce Douglass, Henry S. Ricahrdson, and Gerald M. Mara, eds., Liberalism and Goods, New York and London:Routledge.
PN ⇒ Rousseau 1753
Pol ⇒ Aristotle
Rae, Douglas, et al. 1989: Equalities, Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
RM ⇒ della Volpe 1964
Rousseau, Jean-Jacques 1753 [PN] : “Preface de Narcisse", OEuvres completes, Ⅱ, Paris, Gallimard, 1964. 佐々木康之訳 「ナルシス まえがき」 『ルソー全集』 第11巻,白水社,1980.
Rousseau, Jean-Jacques 1755 [DI] : Discours sur l'origine et les fondaments de l'inegalite parmi les hommes, OEuvres completes, Ⅲ, Paris, Gallimard, 1964. 本田喜代治・平岡昇訳『人間不平等起源論』岩波文庫, 1972.
Rousseau, Jean-Jacques 1755 [EP] : Discours sur l'economie politique, OEuvres completes, Ⅲ, Paris, Gallimard,1964. 河野健二訳『政治経済論』岩波文庫, 1951.
Rousseau, Jean-Jacques 1762 [CS] : Du contract social ou principles du droit politique, OEuvres completes, Ⅲ, Paris, Gallimard, 1964. 桑原武夫・前川貞次郎訳『社会契約論』岩波文庫, 1954.
Rousseau, Jean-Jacques 1765 [CC] : Projet de constitution pour la Corse, OEuvres completes, Ⅲ, Paris, Gallimard,1964. 遅塚忠躬訳『コルシカ憲法草案』『ルソー全集』第5巻,白水社,1979.
Rousseau, Jean-Jacques 1772 [GP] : Considerations sur le gouvernment de Pologne, OEuvres completes, Ⅲ, Paris, Gallimard, 1964. 永見文雄訳『ポーランド統治論』『ルソー全集』第5巻,白水社,1979.
Scanlon, Thomas M. 1982: “Contractualism and Utilitarianism", in Amartya Sen and Bernard Williams, eds., Utilitarianism and Beyond, Cambridge: Cambridge University Press.
Sen, Amartya 1996: “On the Status of Equality", in Political Theory, Vol.24, 1996,No.3.
S.T. ⇒ Thomas Aquinas
Thomas Aquinas [CN] : St. Thomas Aquinas Commentary on the Nicomachean Ethics, tr. C. I. Litzinger, Library of Living Catholic Thought, Vol.1, Chicago: Henry Regnery Com., 1964.
Thomas Aquinas [ST] : St. Thomas Aquinas Summa Theologia, Latin Text and English translation, Notes, Appendices and Glossaries, London and New York: Blackfriars, 1964-1975.
Trachtenberg, Zev M. 1993: Making Citizens: Rousseau's Political Theory of Culture, London and New York: Routledge.
Young, Iris Marion 1990: Justice and the Plitics of Difference, Princeton, NJ: Princeton University Press.
Walzer, Michael 1983: Spheres of Justice: A Defense of Pluralism and Equality, New York: Basic Books.
Westen, Peter 1990: Speaking of Equality: An Analysis of the Rhetorical Force of 'Equality' in Moral and Legal Discourse, Princeton, N.J.: Princeton University Press.